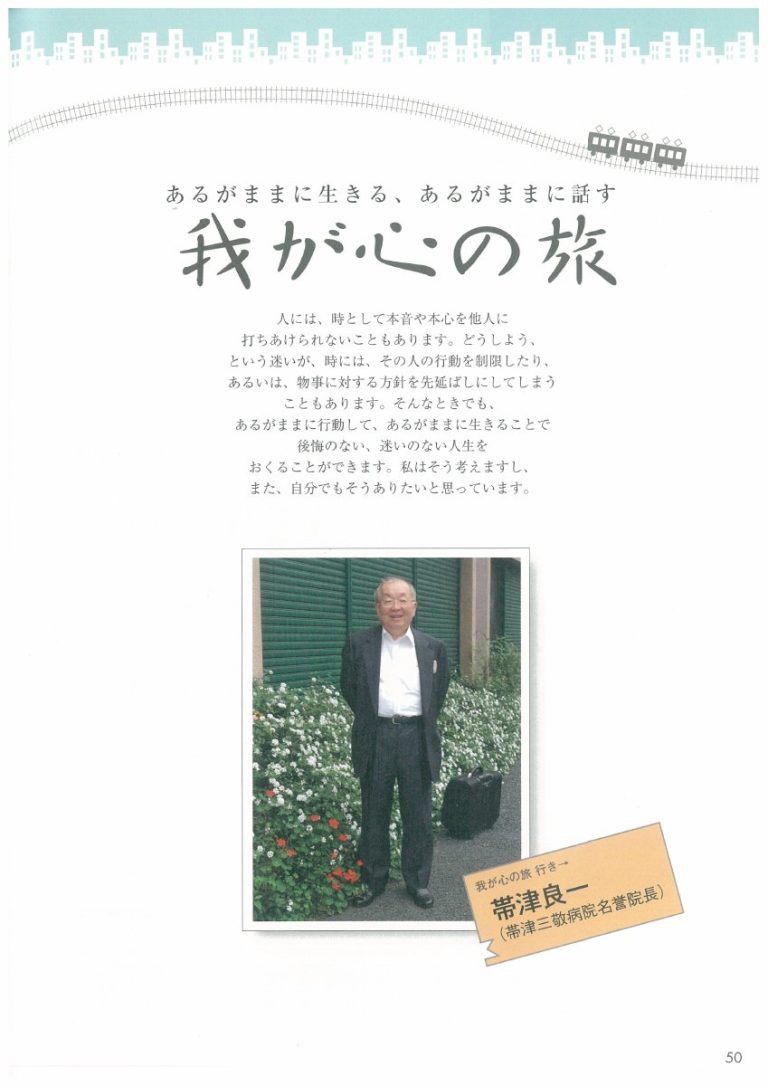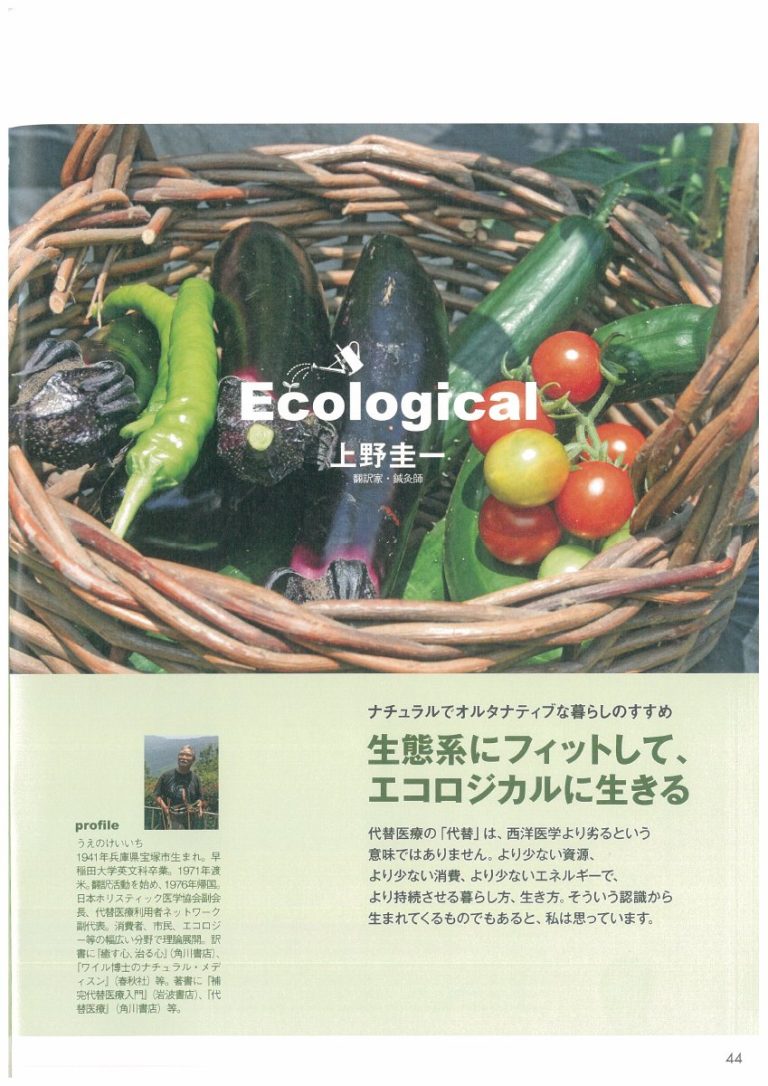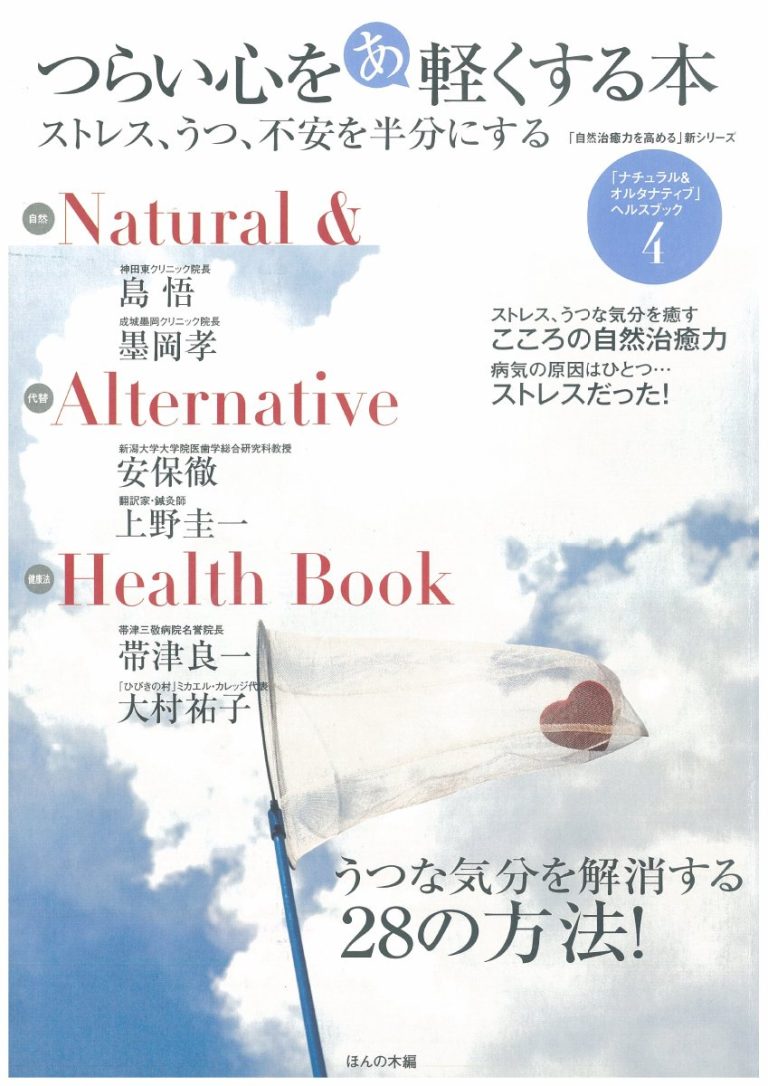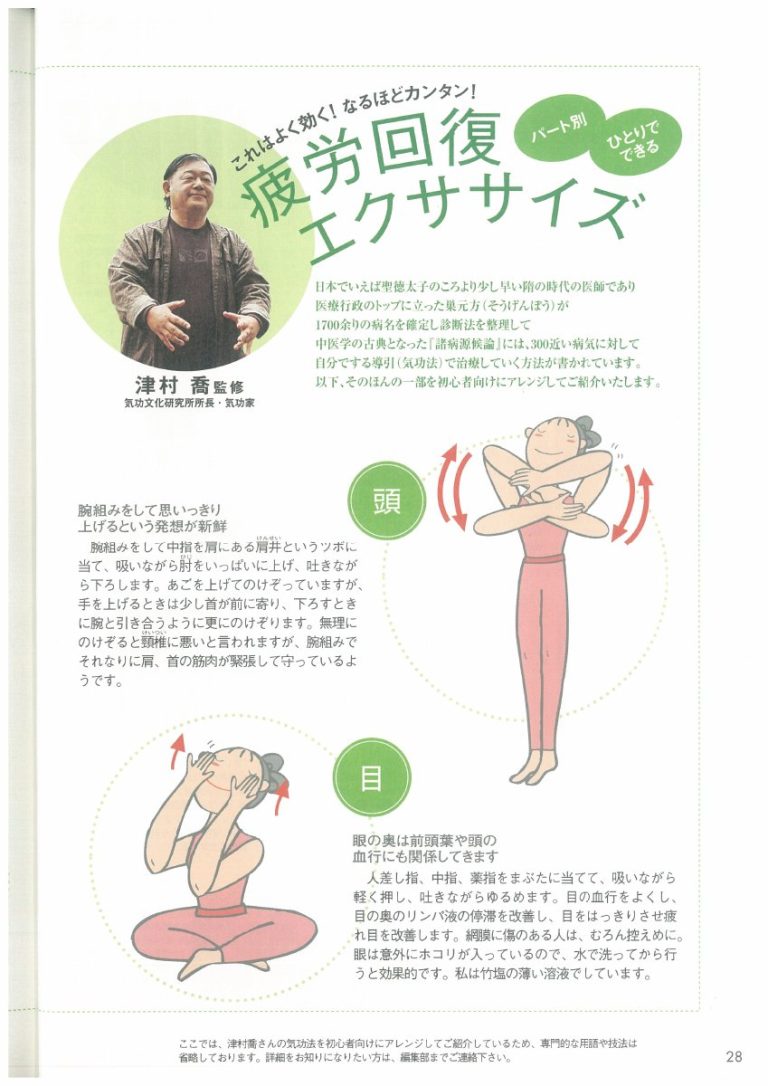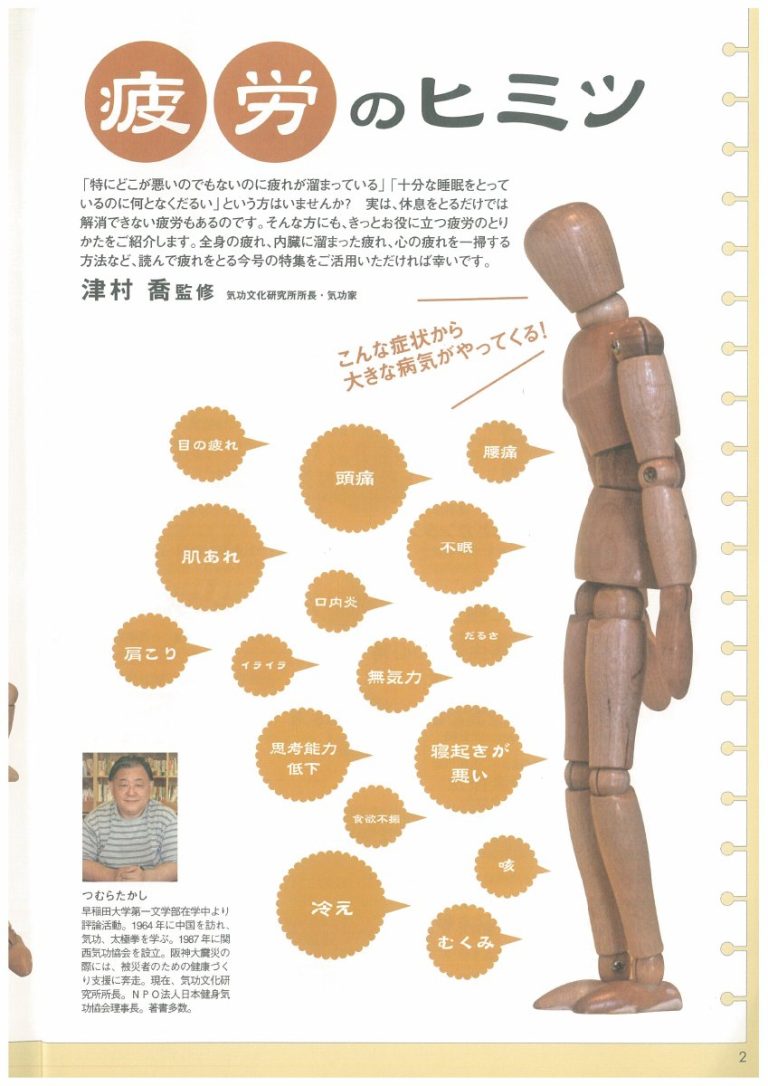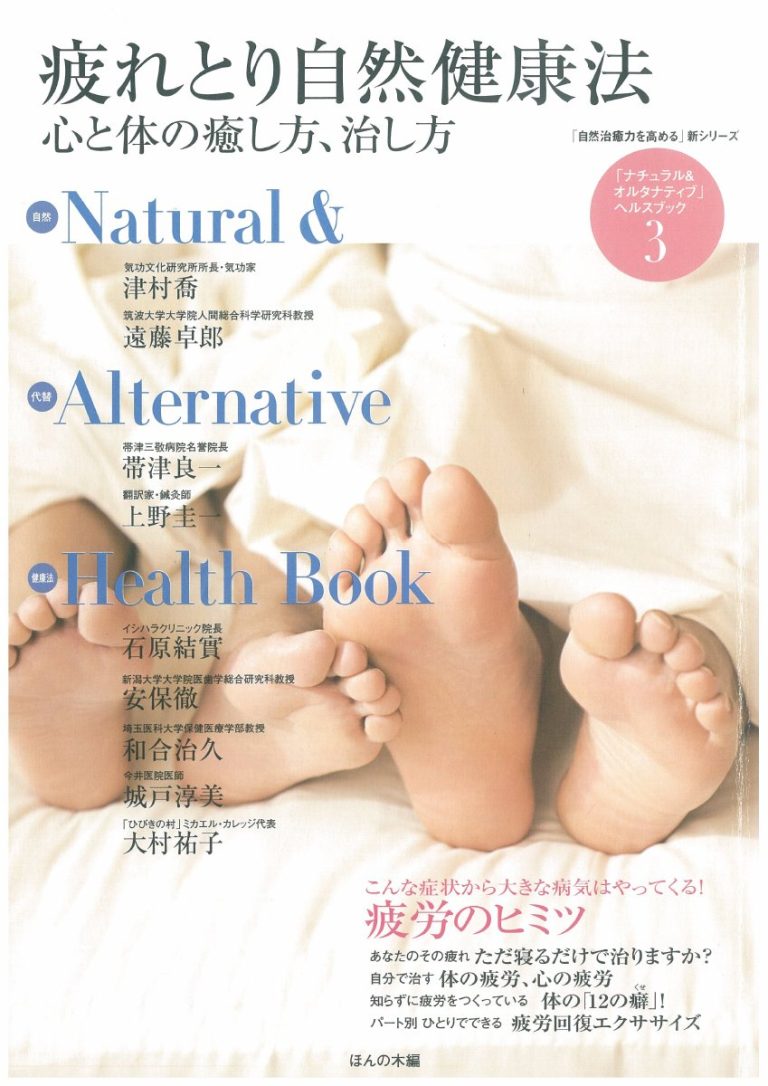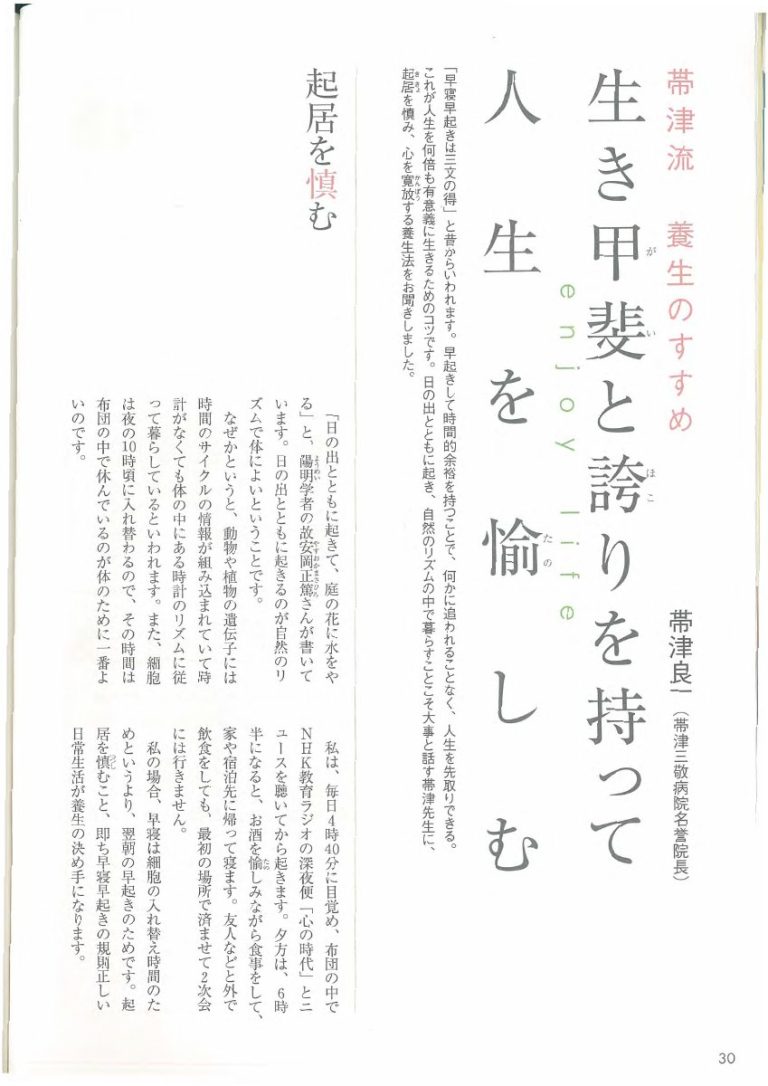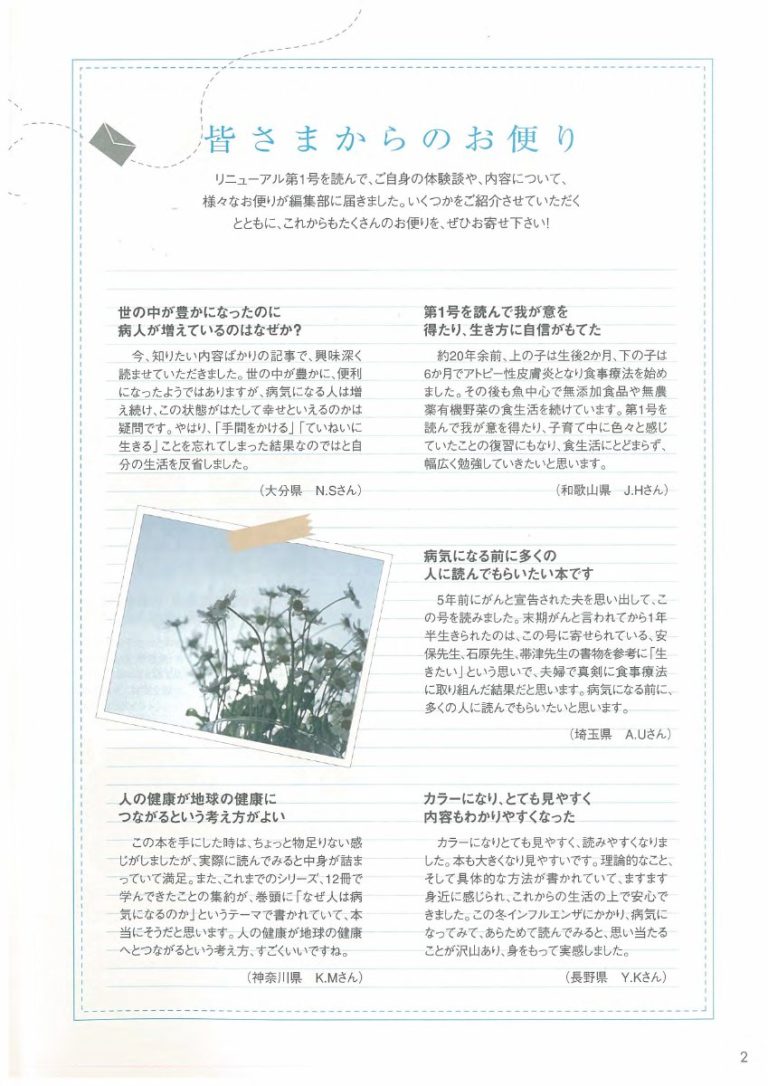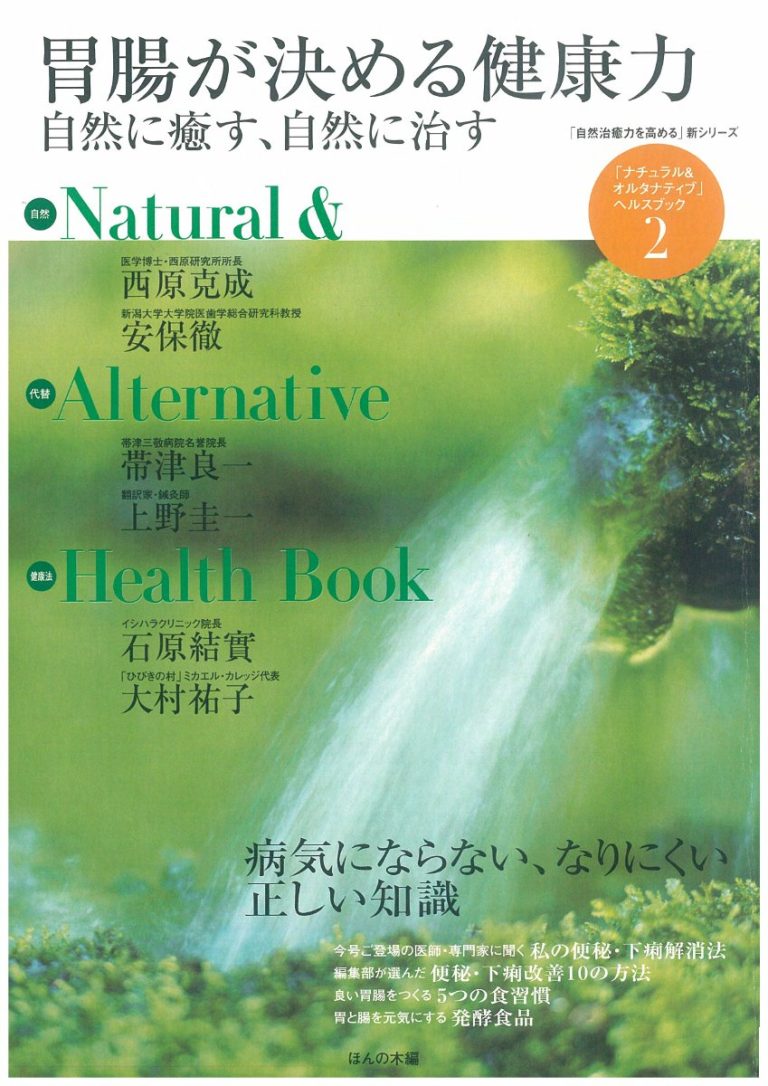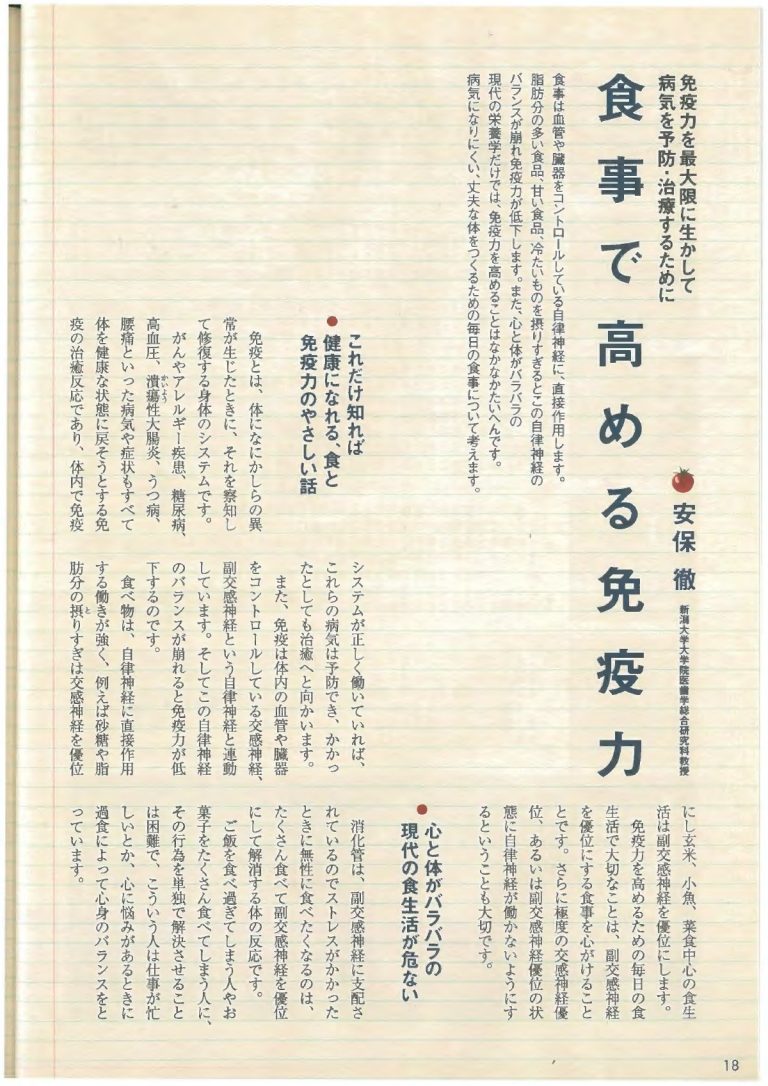- 2025年7月26日
- 2025年7月27日
- 0件
【P.50~】我が心の旅/『「自然治癒力を高める」新シリーズ「ナチュラル・オルタナティブ」ヘルスブック④ つらい心をあ軽くする本』
あるがままに生きる、あるがままに話す 我が心の旅 人には、時として本音や本心を他人に打ちあけられないこともあります。どうしよう、という迷いが、時には、その人の行動を制限したり、あるいは、物事に対する方針を先延ばしにしてしまうこともあります。そんなときでも、あるがままに行動して、あるがままに生きることで後悔のない、迷いのない人生をおくることができます。私はそう考えますし、また、自 […]