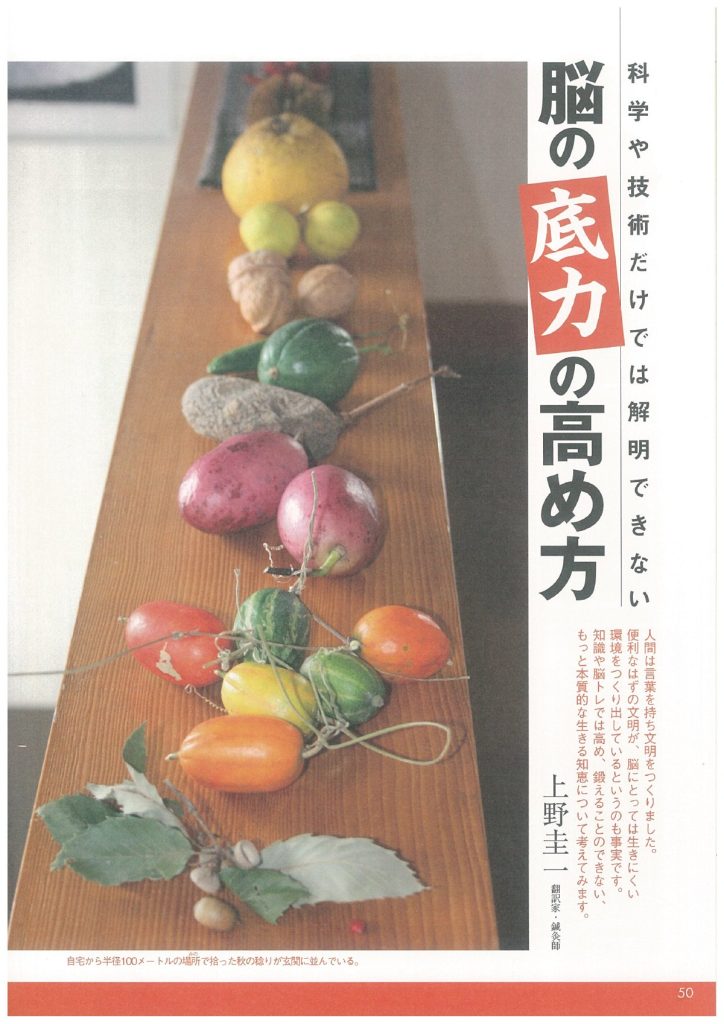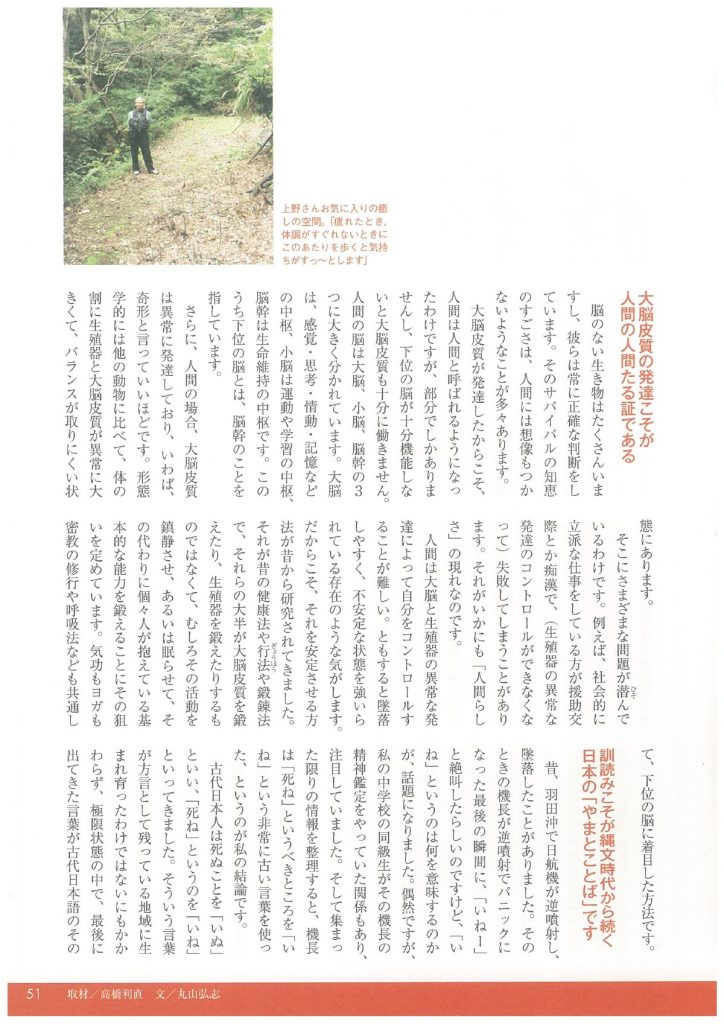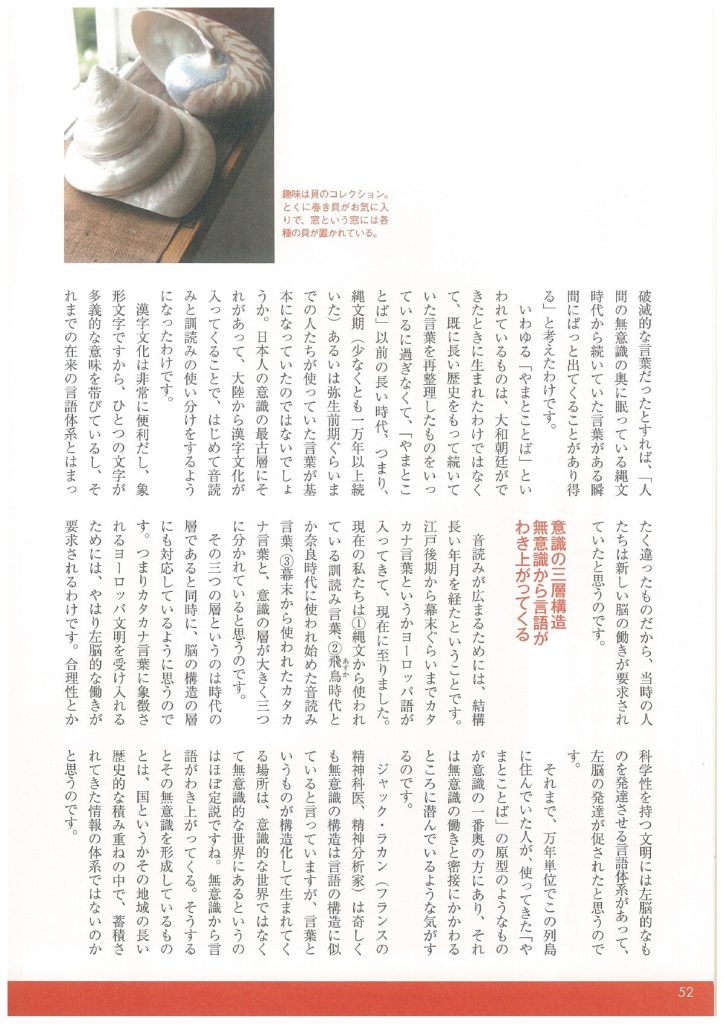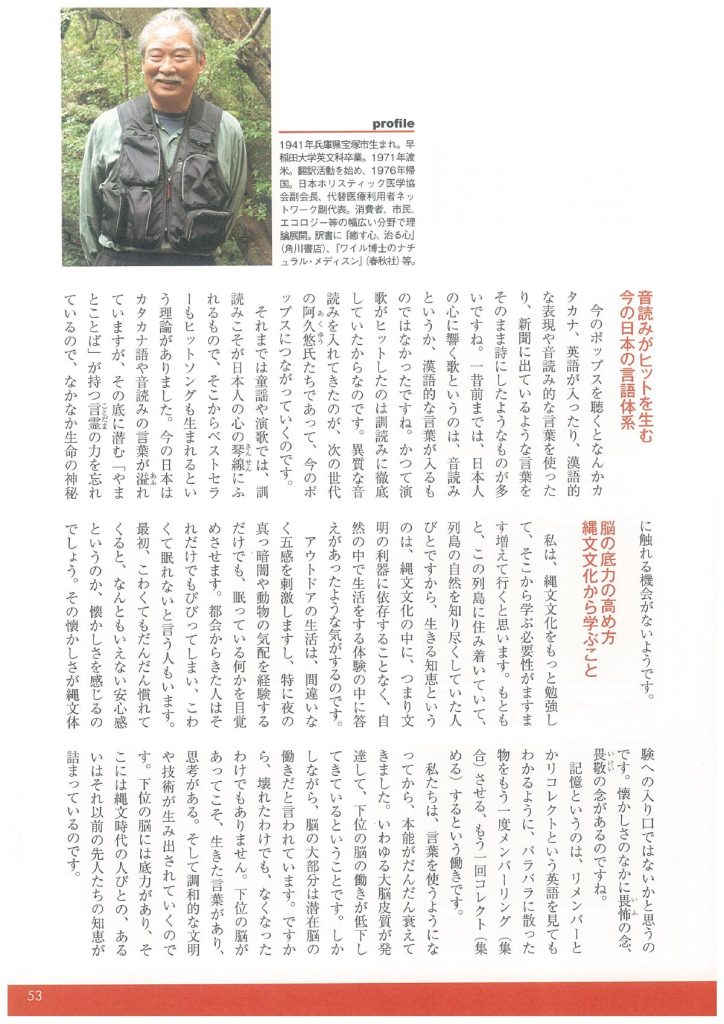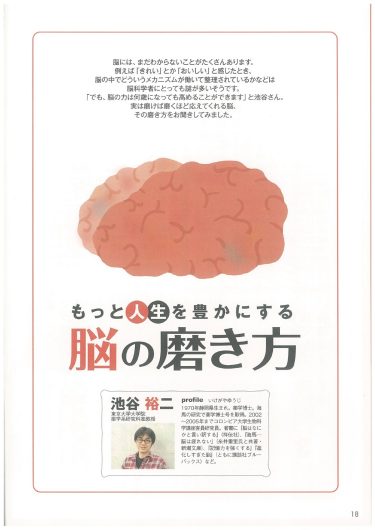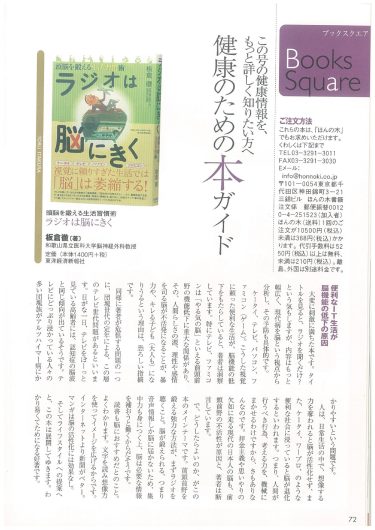科学や技術だけでは解明できない
脳の底力の高め方
人間は言葉を持ち文明をつくりました。
便利なはずの文明が、脳にとっては生きにくい環境をつくり出しているというのも事実です。
知識や脳トレでは高め、鍛えることのできない、もっと本質的な生きる知恵について考えてみます。
大脳皮質の発達こそが人間の人間たる証である
脳のない生き物はたくさんいますし、彼らは常に正確な判断をしています。そのサバイバルの知恵のすごさは、人間には想像もつかないようなことが多々あります。
大脳皮質が発達したからこそ、人間は人間と呼ばれるようになったわけですが、部分でしかありませんし、下位の脳が十分機能しないと大脳皮質も十分に働きません。
人間の脳は大脳、小脳、脳幹の3つに大きく分かれています。大脳は、感覚・思考・情動・記憶などの中枢、小脳は運動や学習の中枢、脳幹は生命維持の中枢です。このうち下位の脳とは、脳幹のことを指しています。
さらに、人間の場合、大脳皮質は異常に発達しており、いわば、奇形と言っていいほどです。形態学的には他の動物に比べて、体の割に生殖器と大脳皮質が異常に大きくて、バランスが取りにくい状態にあります。
そこにさまざまな問題が潜んでいるわけです。例えば、社会的に立派な仕事をしている方が援助交際とか痴漢で、(生殖器の異常な発達のコントロールができなくなって)失敗してしまうことがあります。それがいかにも「人間らしさ」の現れなのです。
人間は大脳と生殖器の異常な発達によって自分をコントロールすることが難しい。ともすると墜落しやすく、不安定な状態を強いられている存在のような気がします。だからこそ、それを安定させる方法が昔から研究されてきました。
それが昔の健康法や行法や鍛錬法で、それらの大半が大脳皮質を鍛えたり、生殖器を鍛えたりするものではなくて、むしろその活動を鎮静させ、あるいは眠らせて、その代わりに個々人が抱えている基本的な能力を鍛えることにその狙いを定めています。気功もヨガも密教の修行や呼吸法なども共通して、下位の脳に着目した方法です。
訓読みこそが縄文時代から続く日本の「やまとことば」です
昔、羽田沖で日航機が逆噴射し、墜落したことがありました。そのときの機長が逆噴射でパニックになった最後の瞬間に、「いねー」と絶叫したらしいのですけど、「いね」というのは何を意味するのかが、話題になりました。偶然ですが、私の中学校の同級生がその機長の精神鑑定をやっていた関係もあり、注目していました。そして集まった限りの情報を整理すると、機長は「死ね」というべきところを「いね」という非常に古い言葉を使った、というのが私の結論です。
古代日本人は死ぬことを「いぬ」といい、「死ね」というのを「いね」といってきました。そういう言葉が方言として残っている地域に生まれ育ったわけではないにもかかわらず、極限状態の中で、最後に出てきた言葉が古代日本語のその破滅的な言葉だったとすれば、「人間の無意識の奥に眠っている縄文時代から続いていた言葉がある瞬間にぱっと出てくることがあり得る」と考えたわけです。
いわゆる「やまとことば」といわれているものは、大和朝廷ができたときに生まれたわけではなくて、既に長い歴史をもって続いていた言葉を再整理したものをいっているに過ぎなくて、「やまとことば」以前の長い時代、つまり、縄文期(少なくとも1万年以上続いた)あるいは弥生前期ぐらいまでの人たちが使っていた言葉が基本になっていたのではないでしょうか。日本人の意識の最古層にそれがあって、大陸から漢字文化が入ってくることで、はじめて音読みと訓読みの使い分けをするようになったわけです。
漢字文化は非常に便利だし、象形文字ですから、ひとつの文字が多義的な意味を帯びているし、それまでの在来の言語体系とはまったく違ったものだから、当時の人たちは新しい脳の働きが要求されていたと思うのです。
意識の三層構造 無意識から言語がわき上がってくる
音読みが広まるためには、結構長い年月を経たということです。江戸後期から幕末ぐらいまでカタカナ言葉というかヨーロッパ語が入ってきて、現在に至りました。現在の私たちは①縄文から使われている訓読み言葉、②飛鳥時代とか奈良時代に使われ始めた音読み言葉、③幕末から使われたカタカナ言葉と、意識の層が大きく3つに分かれていると思うのです。
その3つの層というのは時代の層であると同時に、脳の構造の層にも対応しているように思うのです。つまりカタカナ言葉に象徴されるヨーロッパ文明を受け入れるためには、やはり左脳的な働きが要求されるわけです。合理性とか科学性を持つ文明には左脳的なものを発達させる言語体系があって、左脳の発達が促されたと思うのです。
それまで、万年単位でこの列島に住んでいた人が、使ってきた「やまとことば」の原型のようなものが意識の一番奥の方にあり、それは無意識の働きと密接にかかわるところに潜んでいるような気がするのです。
ジャック・ラカン(フランスの精神科医、精神分析家)は奇しくも無意識の構造は言語の構造に似ていると言っていますが、言葉というものが構造化して生まれてくる場所は、意識的な世界ではなくて無意識的な世界にあるというのはほぼ定説ですね。無意識から言語がわき上がってくる。そうするとその無意識を形成しているものとは、国というかその地域の長い歴史的な積み重ねの中で、蓄積されてきた情報の体系ではないのかと思うのです。
音読みがヒットを生む 今の日本の言語体系
今のポップスを聴くとなんかカタカナ、英語が入ったり、漢語的な表現や音読み的な言葉を使ったり、新聞に出ているような言葉をそのまま詩にしたようなものが多いですね。一昔前までは、日本人の心に響く歌というのは、音読みというか、漢語的な言葉が入るものではなかったですね。かつて演歌がヒットしたのは訓読みに徹底していたからなのです。異質な音読みを入れてきたのが、次の世代の阿久悠氏たちであって、今のポップスにつながっていくのです。
それまでは童謡や演歌では、訓読みこそが日本人の心の琴線にふれるもので、そこからベストセラーもヒットソングも生まれるという理論がありました。今の日本はカタカナ語や音読みの言葉が溢れていますが、その底に潜む「やまとことば」が持つ言霊の力を忘れているので、なかなか生命の神秘に触れる機会がないようです。
脳の底力の高め方 縄文文化から学ぶこと
私は、縄文文化をもっと勉強して、そこから学ぶ必要性がますます増えて行くと思います。もともと、この列島に住み着いていて、列島の自然を知り尽くしていた人びとですから、生きる知恵というのは、縄文文化の中に、つまり文明の利器に依存することなく、自然の中で生活をする体験の中に答えがあったような気がするのです。
アウトドアの生活は、間違いなく五感を刺激しますし、特に夜の真っ暗闇や動物の気配を経験するだけでも、眠っている何かを目覚めさせます。都会からきた人はそれだけでもびびってしまい、こわくて眠れないと言う人もいます。最初、こわくてもだんだん慣れてくると、なんともいえない安心感というのか、懐かしさを感じるのでしょう。その懐かしさが縄文体験への入り口ではないかと思うのです。懐かしさのなかに畏怖の念、畏敬の念があるのですね。
記憶というのは、リメンバーとかリコレクトという英語を見てもわかるように、バラバラに散った物をもう一度メンバーリング(集合)させる、もう1回コレクト(集める)するという働きです。
私たちは、言葉を使うようになってから、本能がだんだん衰えてきました。いわゆる大脳皮質が発達して、下位の脳の働きが低下してきているということです。しかしながら、脳の大部分は潜在脳の働きだと言われています。ですから、壊れたわけでも、なくなったわけでもありません。下位の脳があってこそ、生きた言葉があり、思考がある。そして調和的な文明や技術が生み出されていくのです。下位の脳には底力があり、そこには縄文時代の人びとの、あるいはそれ以前の先人たちの知恵が詰まっているのです。
著者情報
上野圭一 翻訳家・鍼灸師
1941年兵庫県宝塚市生まれ。早稲田大学英文科卒業。1971年渡米。翻訳活動を始め、1976年帰国。日本ホリスティック医学協会副会長、代替医療利用者ネットワーク副代表。消費者、市民、エコロジー等の幅広い分野で理論展開。
クレジット
取材/高橋利直 文/丸山弘志
(『「自然治癒力を高める」新シリーズ「ナチュラル・オルタナティブ」ヘルスブック⑥ 脳から始める新健康習慣 病気の予防と幸福感の高め方』より抜粋)
健康やり直し倶楽部 〜健康の新しい扉を開くPodcast〜
「健康やり直し倶楽部」は、健康と心身の調和をテーマに、高橋編集長と川村氏が雑誌「ナチュラル&オルタネイティブ・ヘルスブック」をもとにお届けするPodcast番組です。自然治癒力を引き出す食事やライフスタイル、心の健康、西洋医学と代替医療の融合まで、あらゆる角度から健康を見つめ直します。エピソードで紹介した特集記事をPDFで公開中!新しい知識と実践で、より豊かな生活を始めてみませんか?