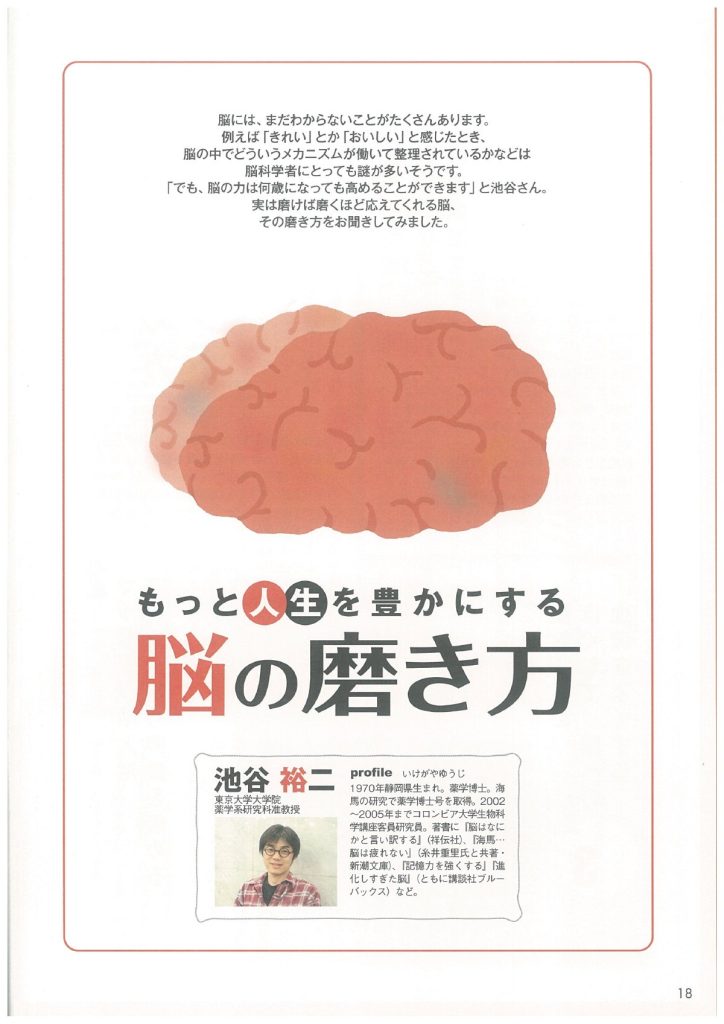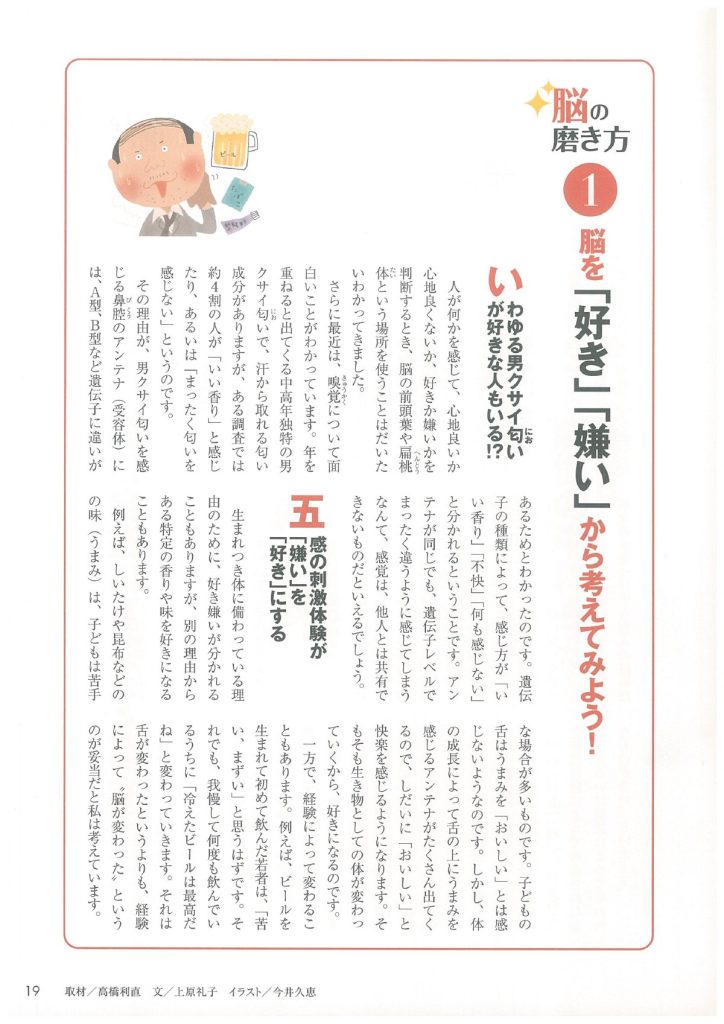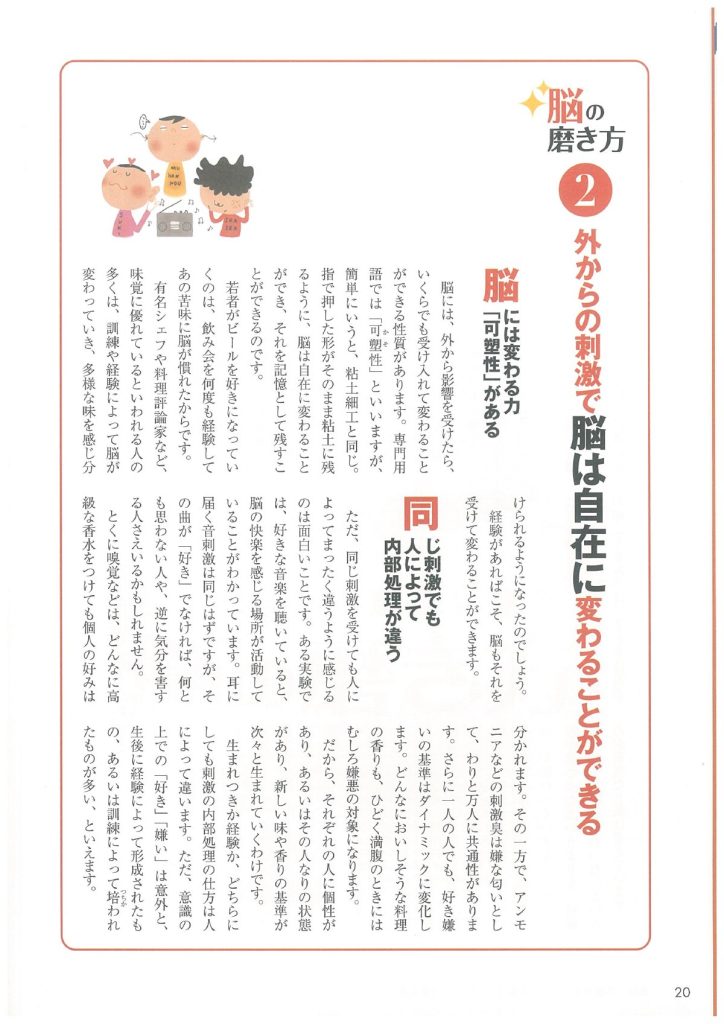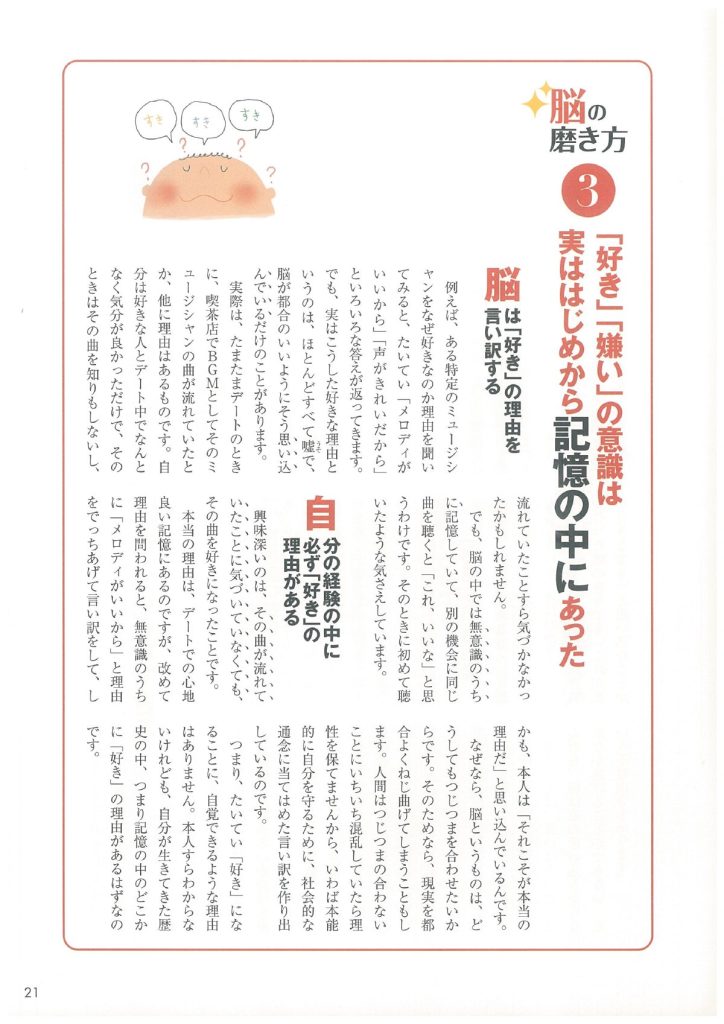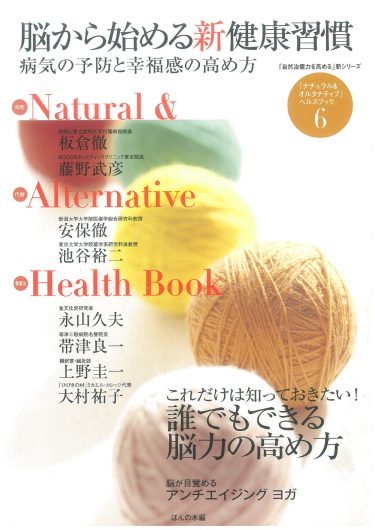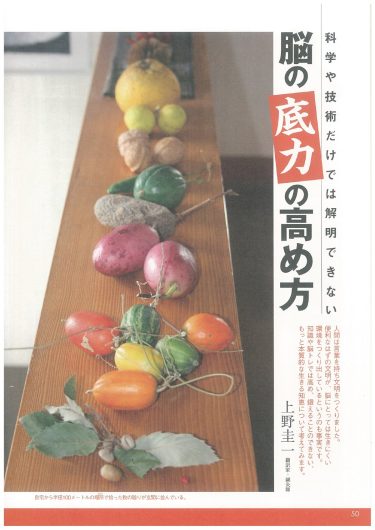もっと人生を豊かにする脳の磨き方
脳には、まだわからないことがたくさんあります。例えば「きれい」とか「おいしい」と感じたとき、脳の中でどういうメカニズムが働いて整理されているかなどは脳科学者にとっても謎が多いそうです。
「でも、脳の力は何歳になっても高めることができます」と池谷さん。
実は磨けば磨くほど応えてくれる脳、その磨き方をお聞きしてみました。
1 脳を「好き」「嫌い」から考えてみよう!
いわゆる男クサイ匂いが好きな人もいる!?
人が何かを感じて、心地良いか心地良くないか、好きか嫌いかを判断するとき、脳の前頭葉や扁桃体という場所を使うことはだいたいいわかってきました。
さらに最近は、嗅覚について面白いことがわかっています。年を重ねると出てくる中高年独特の男クサイ匂いで、汗から取れる匂い成分がありますが、ある調査では約4割の人が「いい香り」と感じたり、あるいは「まったく匂いを感じない」というのです。
その理由が、男クサイ匂いを感じる鼻腔のアンテナ(受容体)には、A型、B型など遺伝子に違いがあるためとわかったのです。遺伝子の種類によって、感じ方が「いい香り」「不快」「何も感じない」と分かれるということです。アンテナが同じでも、遺伝子レベルでまったく違うように感じてしまうなんて、感覚は、他人とは共有できないものだといえるでしょう。
五感の刺激体験が「嫌い」を「好き」にする
生まれつき体に備わっている理由のために、好き嫌いが分かれることもありますが、別の理由からある特定の香りや味を好きになることもあります。
例えば、しいたけや昆布などの味(うまみ)は、子どもは苦手な場合が多いものです。子どもの舌はうまみを「おいしい」とは感じないようなのです。しかし、体の成長によって舌の上にうまみを感じるアンテナがたくさん出てくるので、しだいに「おいしい」と快楽を感じるようになります。そもそも生き物としての体が変わっていくから、好きになるのです。
一方で、経験によって変わることもあります。例えば、ビールを生まれて初めて飲んだ若者は、「苦い、まずい」と思うはずです。それでも、我慢して何度も飲んでいるうちに「冷えたビールは最高だね」と変わっていきます。それは舌が変わったというよりも、「経験によって、脳が変わった」というのが妥当だと私は考えています。
2 外からの刺激で脳は自在に変わることができる
脳には「可塑性」がある
脳には、外から影響を受けたら、いくらでも受け入れて変わることができる性質があります。専門用語では「可塑性」といいますが、簡単にいうと、粘土細工と同じ。指で押した形がそのまま粘土に残るように、脳は自在に変わることができ、それを記憶として残すことができるのです。
若者がビールを好きになっていくのは、飲み会を何度も経験してあの苦味に脳が慣れたからです。
有名シェフや料理評論家など、味覚に優れているといわれる人の多くは、訓練や経験によって脳が変わっていき、多様な味を感じ分けられるようになったのでしょう。経験があればこそ、脳もそれを受けて変わることができます。
同じ刺激でも人によって内部処理が違う
ただ、同じ刺激を受けても人によってまったく違うように感じるのは面白いことです。ある実験では、好きな音楽を聴いていると、脳の快楽を感じる場所が活動していることがわかっています。耳に届く音刺激は同じはずですが、その曲が「好き」でなければ、何とも思わない人や、逆に気分を害する人さえいるかもしれません。
とくに嗅覚などは、どんなに高級な香水をつけても個人の好みは分かれます。その一方で、アンモニアなどの刺激臭は嫌な匂いとして、わりと万人に共通性があります。さらに一人の人でも、好き嫌いの基準はダイナミックに変化します。どんなにおいしそうな料理の香りも、ひどく満腹のときにはむしろ嫌悪の対象になります。
だから、それぞれの人に個性があり、あるいはその人なりの状態があり、新しい味や香りの基準が次々と生まれていくわけです。
生まれつきか経験か、どちらにしても刺激の内部処理の仕方は人によって違います。ただ、意識の上での「好き」「嫌い」は意外と、生後に経験によって形成されたもの、あるいは訓練によって培われたものが多い、といえます。
3 「好き」「嫌い」の意識は実ははじめから記憶の中にあった
脳は「好き」の理由を言い訳する
例えば、ある特定のミュージシャンをなぜ好きなのか理由を聞いてみると、たいてい「メロディがいいから」「声がきれいだから」といろいろな答えが返ってきます。でも、実はこうした好きな理由というのは、ほとんどすべて嘘で、脳が都合のいいようにそう思い込んでいるだけのことがあります。
実際は、たまたまデートのときに、喫茶店でBGMとしてそのミュージシャンの曲が流れていたとか、他に理由はあるものです。自分は好きな人とデート中でなんとなく気分が良かっただけで、そのときはその曲を知りもしないし、流れていたことすら気づかなかったかもしれません。
でも、脳の中では無意識のうちに記憶していて、別の機会に同じ曲を聴くと「これ、いいな」と思うわけです。そのときに初めて聴いたような気さえしています。
自分の経験の中に必ず「好き」の理由がある
興味深いのは、その曲が流れていたことに気づいていなくても、その曲を好きになったことです。
本当の理由は、デートでの心地良い記憶にあるのですが、改めて理由を問われると、無意識のうちに「メロディがいいから」と理由をでっちあげて言い訳をして、しかも、本人は「それこそが本当の理由だ」と思い込んでいるんです。
なぜなら、脳というものは、どうしてもつじつまを合わせたいからです。そのためなら、現実を都合よくねじ曲げてしまうこともします。人間はつじつまの合わないことにいちいち混乱していたら理性を保てませんから、いわば本能的に自分を守るために、社会的な通念に当てはめた言い訳を作り出しているのです。
つまり、たいてい「好き」になることに、自覚できるような理由はありません。本人すらわからないけれども、自分が生きてきた歴史の中、つまり記憶の中のどこかに「好き」の理由があるはずなのです。
4 人は思い込み次第でなんでも「好き」になることができる
自分の脳が好きな香りや味覚を作っている
好き嫌いというのは、表面的に意識の上で判断することではなく、いろいろな物事を経験してきた結果として作られています。つまり、記憶が好き嫌いを作るのです。
例えば、アロマオイルなどをブレンドして、好みの香りを作ってくれる調香師という職業がありますね。調香師は、好きな風景や好きな色など、さまざまな好みを聞いてイメージを膨らませ、その人に合った香りを作るといいます。
人間は日々変わっていく生き物ですから、調香師は話を聞きながらその瞬間に合わせた香りを作っていくのでしょう。香りをある方向性に導いているかもしれません。もし、その人が海に関して良い記憶があれば、海を思わせる香りも、色も風景も好きなものになるはずです。これは、脳が無意識のうちに好きなもの同士を結びつけたためで、こうした「好き」同士の結びつけも脳の仕事の1つです。
脳は「好き」と信じればいつまでも「好き」でいられる
ただ、「これがあなたの香り」と言われても、本当に自分が好きな香りなのか、実はわかりません。でも、言ってしまえば、調香師が作った嘘の香りでも「これが私の好きな香り」と思い込むことができれば、それでいいのです。
「私はこれが好き」と信じている香りを嗅いでいるだけで、その香りを本当に好きになっていくし、心地良くなっていく。だから、それはそれで良いことだと私は思います。
似たような例に、プレシーボ(プラシボ)効果があります。実際は片栗粉や小麦粉で作ったにせの錠剤でも、「効く」と信じていれば、効くことがあるというものです。
ただし、薬をくれる医者を信頼している場合にしか効きませんが、それでも脳が「効く」と思い込むことによって効果は表れるのです。逆にいえば、悪いほうへ思い込んだら、脳はその思い込みからなかなか逃げることができない、という不自由さもあります。
5 同じ1日を過ごすならワクワク生きる方がずっと楽しい
あなたの人生はあなた自身で心地良くできます
心理学者が行なったある実験を例にとりましょう。唇に触れないよう歯だけでペンを縦にくわえている人と、歯には触れないよう唇だけでペンを横にくわえている人にそれぞれ同じ漫画を読んでもらうのです。同じ内容なのに、前者のほうが面白く感じるといいます。
なぜかというと、ペンを歯でくわえると顔の表情が笑顔に似て、笑顔を作るときと同じ筋肉を動かすことになるからです。すると「今、自分は笑っている」とまず脳が認め、そしてその状況を「笑っているから、目の前のことは楽しいに違いない」と解釈します。
こんな仕組みがあるなら、笑顔でいるほうがいいと思いませんか。私もそうなんですが、笑顔を作ると楽しくなるように脳に仕組まれていると知った後は、どんなときでも笑顔を作るように心がけています。笑顔を作れば、本当に楽しい気持ちになってきます。
マンネリ化に打ち勝つ努力も時には必要です
朝起きて「イヤだな、いつもの一日が始まる」と思ったらアウトということです。それよりも、サッと起きて「今日は何が起こるだろう?」と思っていたほうがよっぽどいい。脳はなにかと思い込みがちで決めつけたがりですから、悪い思いこみに任せてしまうなんて、もったいないと思います。
たしかに脳にとっては、日常生活における慣れを「当たり前」と決めつける機能(マンネリ化)は必要です。しかし、脳のマンネリ化を認めすぎてしまうと、新鮮なときめきやワクワクを感じられなくなってしまいます。だから印象にも残らなくなり、記憶力が一見低下したとか、あるいは脳が老化したと思ったりするのです。
日常生活の中でときめきやワクワクを感じながら生きることは、良い生き方につながると思います。いつまでもワクワクのアンテナを張って、笑顔でいれば、脳はいくらでも応えてくれるのですから。
著者情報
池谷裕二
東京大学大学院 薬学系研究科准教授
1970年静岡県生まれ。薬学博士。海馬の研究で薬学博士号を取得。2002〜2005年までコロンビア大学生物科学講座客員研究員。
クレジット
取材/高橋利直 文/上原礼子 イラスト/今井久恵
(『「自然治癒力を高める」新シリーズ「ナチュラル・オルタナティブ」ヘルスブック⑥ 脳から始める新健康習慣 病気の予防と幸福感の高め方』より抜粋)
健康やり直し倶楽部 〜健康の新しい扉を開くPodcast〜
「健康やり直し倶楽部」は、健康と心身の調和をテーマに、高橋編集長と川村氏が雑誌「ナチュラル&オルタネイティブ・ヘルスブック」をもとにお届けするPodcast番組です。自然治癒力を引き出す食事やライフスタイル、心の健康、西洋医学と代替医療の融合まで、あらゆる角度から健康を見つめ直します。エピソードで紹介した特集記事をPDFで公開中!新しい知識と実践で、より豊かな生活を始めてみませんか?