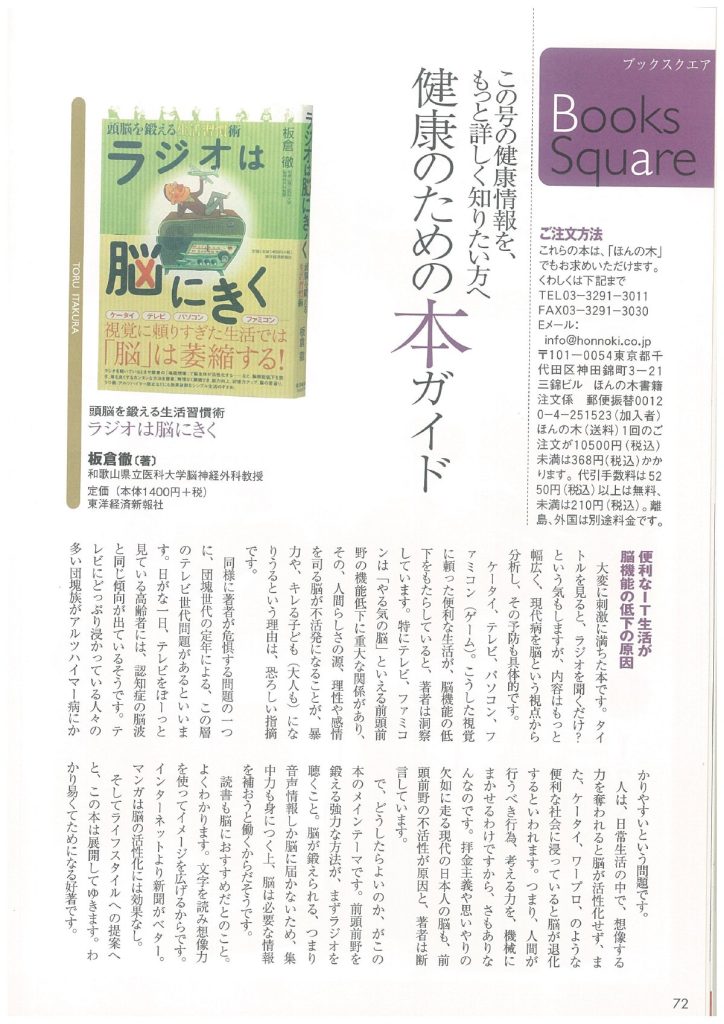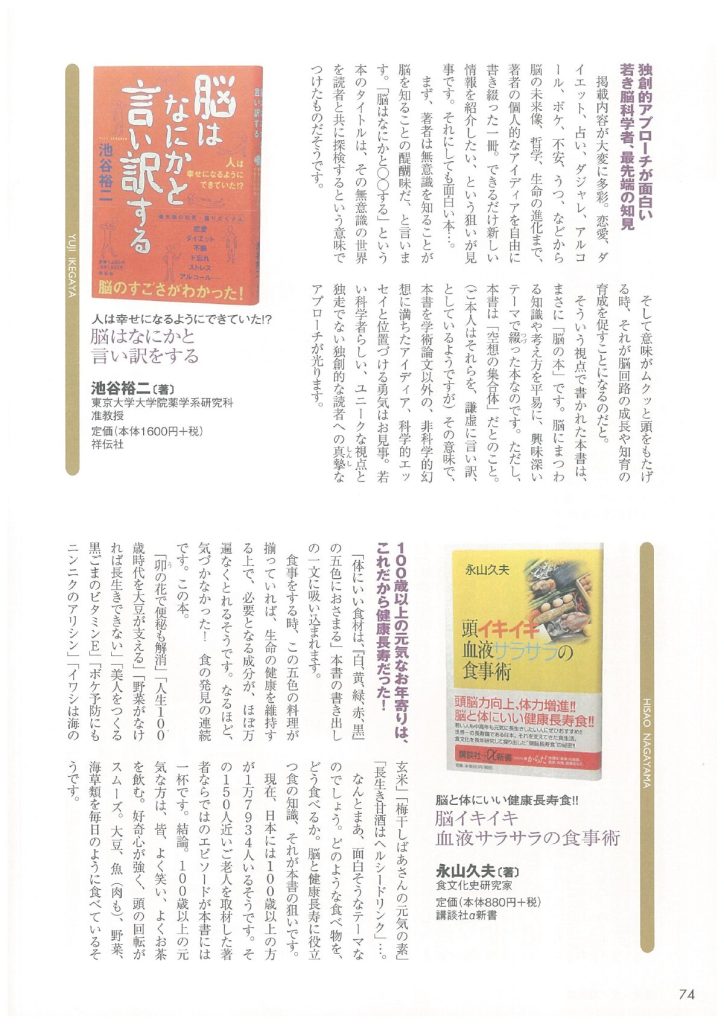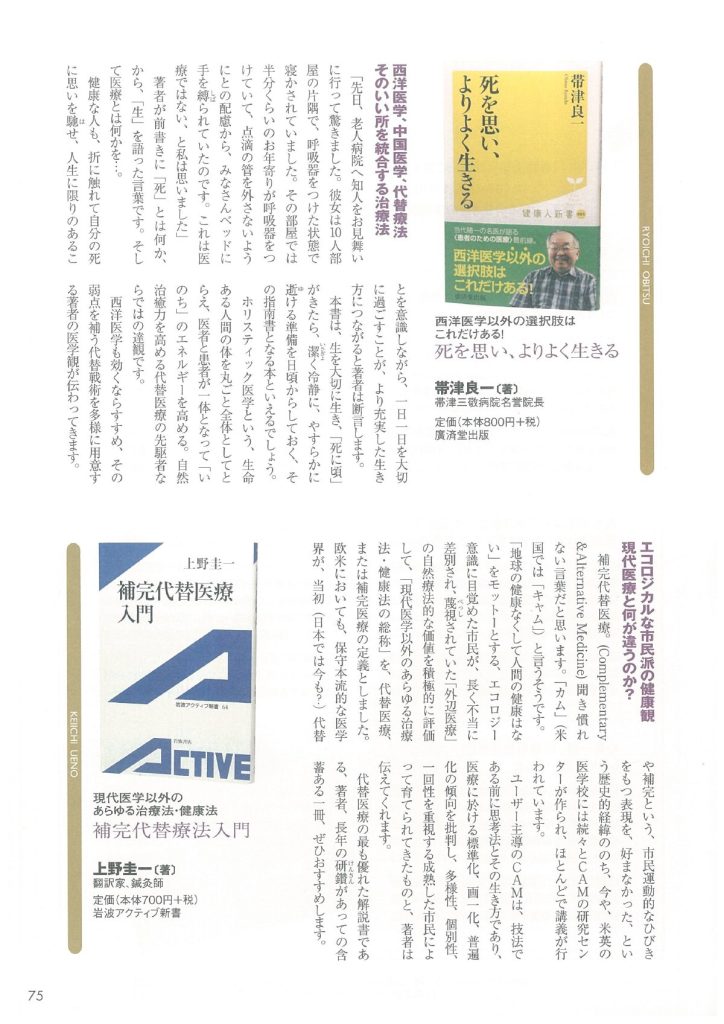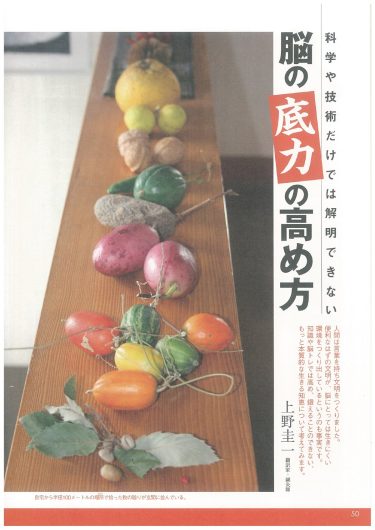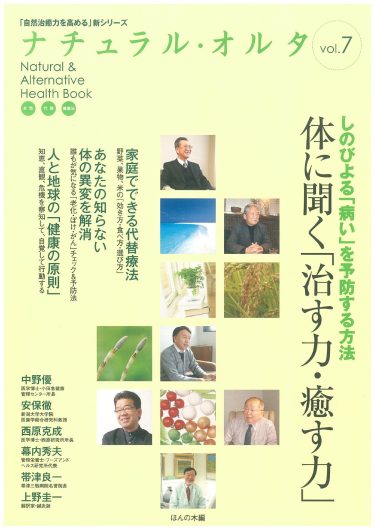健康のための本ガイド
この号の健康情報を、もっと詳しく知りたい方へ
頭脳を鍛える生活習慣術 ラジオは脳にきく
便利なIT生活が脳機能低下の原因
大変に便利な世の中です。タイトルを見ると、ラジオを聞くだけ?という気もしますが、内容はもっと幅広く、現代病を脳という視点から分析し、その予防を具体的に示す。
ケータイ、テレビ、パソコン、視覚情報に頼りすぎた生活は、脳疲労による機能低下の大きな原因。特にテレビ・ファミコンで育った若者は、前頭前野の機能低下に重大な問題があり、その人間の不満の源、神経症や精神病、人間関係が不活発になることが暴露される。子供にも「大人」にも、集中力や、キレる子にも、忍耐力、思考力、学習意欲の低下など、憂うべき問題が起こりうる、と著者は警鐘を鳴らす。
同時に著者が危惧する問題の1つに、団塊の世代の加齢による、この層のテレビ視聴時間の多さがあるといいます。一日かなりの時間、テレビとじっとにらめっこ。これでは脳が働きを停止し、認知症の前段階と同様の傾向が出ていそうです。テレビにどっぷり浸かっている多くの人、多い団塊世代がアルツハイマー病にかかりやすいという問題です。
人は、日常生活の中で、想像する力、夢見る力を奪われずに、幸せに生きる権利がある。ケータイ、ワープロ、のような便利な社会に生きていると脳の退化がすすむといわれます。つまり、人間が行うべき行為、考える力を、機械にまかせすぎるからです。押さえどころのある簡潔な文章、挿絵も思いのほか多いのです。拝金主義にさいなまれる現代社会に生きる現代人の脳は、前頭前野の不活性が原因と、著者は断言しています。
では、どうしたらいいのか。がこの本のメインテーマです。前頭前野を鍛える効果的な方法が、まずラジオを聴くこと。ラジオは聴覚から、つまり音声言語として脳に届くため、想像力を働かせ、脳を活性化させる。読書も脳を働かせるそうです。
読書は脳におすすめなのだそうです。よくわかります。文字を読み想像力を駆使しイメージを広げるからです。インターネットよりは新聞がベター。マンガは脳の活性化には効果的。
そしてライフスタイルへの提案へと、この本を展開してゆきます。わかり易くてためになる好著です。
老化、認知症、若者の不安… 現代の病気は脳疲労が原因
裏帯の「実はあなたも脳疲労?」をまずお読み下さい。
- 途中であるいは朝早く目が覚める
- 寝つきが悪い
- 食事がおいしくない
- 便秘する
- 体を使わないのにへとへと
- 気持ちが暗くなる
- 希望が持てない
- 考えがまとまらない
- イライラする
- 不安である
- 自分は価値のない人間だと思う
(毎日ある、が1項目以上。週2〜3日以上が3項目以上、いずれかに該当すれば、あなたも脳疲労の可能性があります。さて、いかがですか)
九州大学健康科学センターで研究、教師、医師を務めた著者は、人はなぜ病気になるのか、生活習慣が悪くなるのかを、こう仮説として主張します。「生活習慣病の始まりは『脳疲労』」だと。脳を癒すことがその予防法だというのです。またその理論を膨大なデータで検証をしてきました。内科学を脳科学で解明しようとする著者の理論を、わかりやすく、日常的な例を使って、説明してくれる本です。
現代の病がスッキリわかります。
健康に100歳まで生きられる 可能性を追求した人間全体論
西洋医学が手にした薬(化学物質)は代謝を阻害し、薬物というよりは生体毒としての意味合いの方が強い、そう著者は喝破します。本書の全体を貫く考え方は、これからめざす、新しい医学の全体像を解き明かすことと言えます。
「自然の征服よりも自然との融和を民族の歩みとしてきた日本人が、世界で最初に新しい医学や、医療を生み出す可能性もあるのではないか、それを可能にするキーワードは、全身を統合するシステムの中にあると思う」…著者の前書きの一部です。
そして、自律神経(調節系)、白血球(防御系)、体温(循環系)が、その全体把握のキーワードである、としています。
病気とは、その三者の偏りが原因で、疾患から逃れる方策として、またアンチ・エイジングを進めるためにも、体を臓器別に理解したり、西洋医・薬を服用し、処方しては破綻におちいると説明します。
新しい医学の基本、生き方の偏り、生体反応、心とからだ、思い込みと病気、治療への道、生命進化。これらを1チャプター2頁の、エッセイ風タッチで解明する展開と、幅広いエピソードに酔える内容です。
独創的アプローチが面白い 若き脳科学者、最先端の知見
掲載内容が大変に多彩。恋愛、ダイエット、占い、ダジャレ、アルコール、ボケ、不安、うつ、などから脳の未来像、哲学、生命の進化まで、著者の個人的なアイディアを自由に書き綴った一冊。できるだけ新しい情報を紹介したい、という狙いが見事です。それにしても面白い本…。
まず、著者は無意識を知ることが脳を知ることの醍醐味だ、と言います。「脳はなにかと○○する」という本のタイトルは、その無意識の世界を読者と共に探検するという意味でつけたものだそうです。
そして意味がムクッと頭をもたげる時、それが脳回路の成長や知育の育成を促すことになるのだと。
そういう視点で書かれた本書は、まさに「脳の本」です。脳にまつわる知識や考え方を平易に、興味深いテーマで綴った本なのです。ただし、本書は「空想の集合体」だとのこと。(ご本人はそれらを、謙虚に言い訳、としているようですが)その意味で、本書を学術論文以外の、非科学的幻想に満ちたアイディア、科学的エッセイと位置づける勇気はお見事。若い科学者らしい、ユニークな視点と独走でない独創的な読者への真摯なアプローチが光ります。
100歳以上の元気なお年寄りは、 これだから健康長寿だった!
「体にいい食材は、『白、黄、緑、赤、黒』の五色におさまる」本書の書き出しの一文に吸い込まれます。
食事をする時、この五色の料理が揃っていれば、生命の健康を維持する上で、必要となる成分が、ほぼ万遍なくとれるそうです。なるほど、気づかなかった! 食の発見の連続です。この本。
「卯の花で便秘も解消」「人生100歳時代を大豆が支える」「野菜がなければ長生きできない」「美人をつくる黒ごまのビタミンE」「ボケ予防にもニンニクのアリシン」「イワシは海の玄米」「梅干しばあさんの元気の素」「長生き甘酒はヘルシードリンク」…。
なんとまあ、面白そうなテーマなのでしょう。どのような食べ物を、どう食べるか。脳と健康長寿に役立つ食の知識、それが本書の狙いです。
現在、日本には100歳以上の方が1万7934人いるそうです。その150人近いご老人を取材した著者ならではのエピソードが本書には一杯です。結論。100歳以上の元気な方は、皆、よく笑い、よくお茶を飲む。好奇心が強く、頭の回転がスムーズ。大豆、魚(肉も)、野菜、海草類を毎日のように食べているそうです。
西洋医学、中国医学、代替療法 そのいい所を統合する治療法
「先日、老人病院へ知人をお見舞いに行って驚きました。彼女は10人部屋の片隅で、呼吸器をつけた状態で寝かされていました。その部屋では半分くらいのお年寄りが呼吸器をつけていて、点滴の管を外さないようにとの配慮から、みなさんベッドに手を縛られていたのです。これは医療ではない、と私は思いました」
著者が前書きに「死」とは何か、から、「生」を語った言葉です。そして医療とは何かを…。
健康な人も、折に触れて自分の死に思いを馳せ、人生に限りのあることを意識しながら、一日一日を大切に過ごすことが、より充実した生き方につながると著者は断言します。
本書は、生を大切に生き、「死に頃」がきたら、潔く冷静に、やすらかに逝ける準備を日頃からしておく、その指南書となる本といえるでしょう。
ホリスティック医学という、生命ある人間の体を丸ごと全体としてとらえ、医者と患者が一体となって「いのち」のエネルギーを高める。自然治癒力を高める代替医療の先駆者ならではの達観です。
西洋医学も効くならすすめ、その弱点を補う代替戦術を多様に用意する著者の医学観が伝わってきます。
エコロジカルな市民派の健康観 現代医療と何が違うのか?
補完代替医療。(Complementary &Alternative Medicine) 聞き慣れない言葉だと思います。「カム」(米国では「キャム」)と言うそうです。
「地球の健康なくして人間の健康はない」をモットーとする、エコロジー意識に目覚めた市民が、長く不当に差別され、蔑視されていた「外辺医療」の自然療法的な価値を積極的に評価して、「現代医学以外のあらゆる治療法・健康法の総称」を、代替医療、または補完医療の定義としました。
欧米においても、保守本流的な医学界が、当初(日本では今も?)代替や補完という、市民運動的なひびきをもつ表現を、好まなかった、という歴史的経緯ののち、今や、米英の医学校には続々とCAMの研究センターが作られ、ほとんどで講義が行われています。
ユーザー主導のCAMは、技法である前に思考法とその生き方であり、医療に於ける標準化、画一化、普遍化の傾向を批判し、多様性、個別性、1回性を重視する成熟した市民によって育てられてきたものと、著者は伝えてくれます。
代替医療の最も優れた解説書である、著者、長年の研鑽があっての含蓄ある一冊、ぜひおすすめします。
著者情報
板倉徹〔著〕 和歌山県立医科大学脳神経外科教授
藤野武彦〔著〕 九州大学名誉教授
安保徹〔著〕 新潟大学大学院医歯学総合研究科教授
池谷裕二〔著〕 東京大学大学院薬学系研究科 准教授
永山久夫〔著〕 食文化史研究家
帯津良一〔著〕 帯津三敬病院名誉院長
上野圭一〔著〕 翻訳家、鍼灸師
クレジット
構成・文/編集部
(『「自然治癒力を高める」新シリーズ「ナチュラル・オルタナティブ」ヘルスブック⑥ 脳から始める新健康習慣 病気の予防と幸福感の高め方』より抜粋)
健康やり直し倶楽部 〜健康の新しい扉を開くPodcast〜
「健康やり直し倶楽部」は、健康と心身の調和をテーマに、高橋編集長と川村氏が雑誌「ナチュラル&オルタネイティブ・ヘルスブック」をもとにお届けするPodcast番組です。自然治癒力を引き出す食事やライフスタイル、心の健康、西洋医学と代替医療の融合まで、あらゆる角度から健康を見つめ直します。エピソードで紹介した特集記事をPDFで公開中!新しい知識と実践で、より豊かな生活を始めてみませんか?