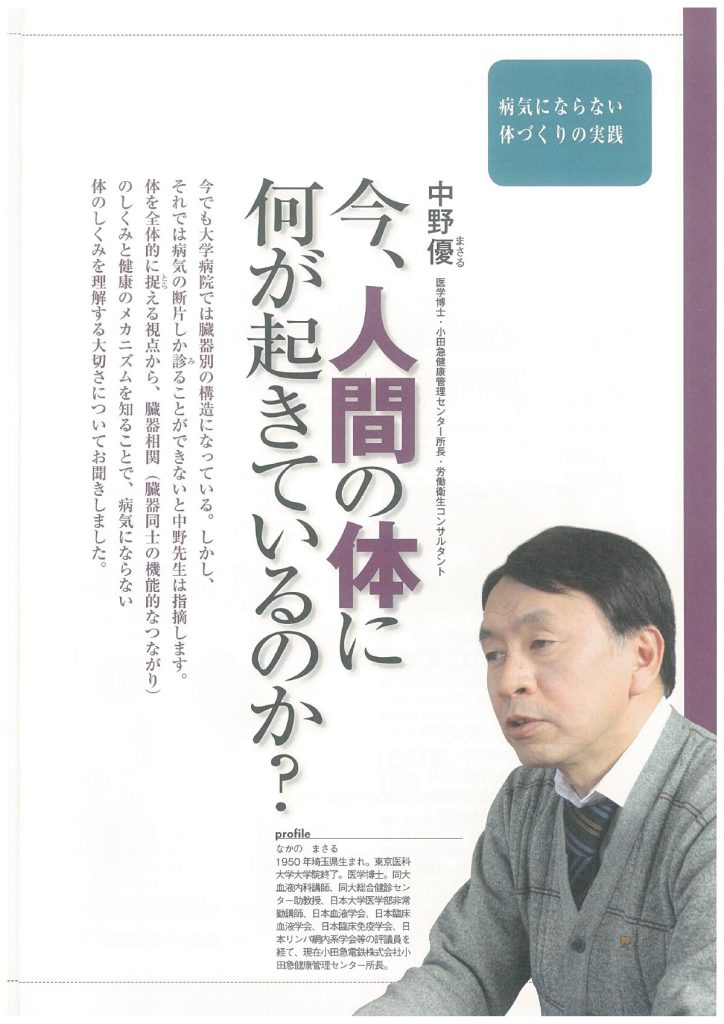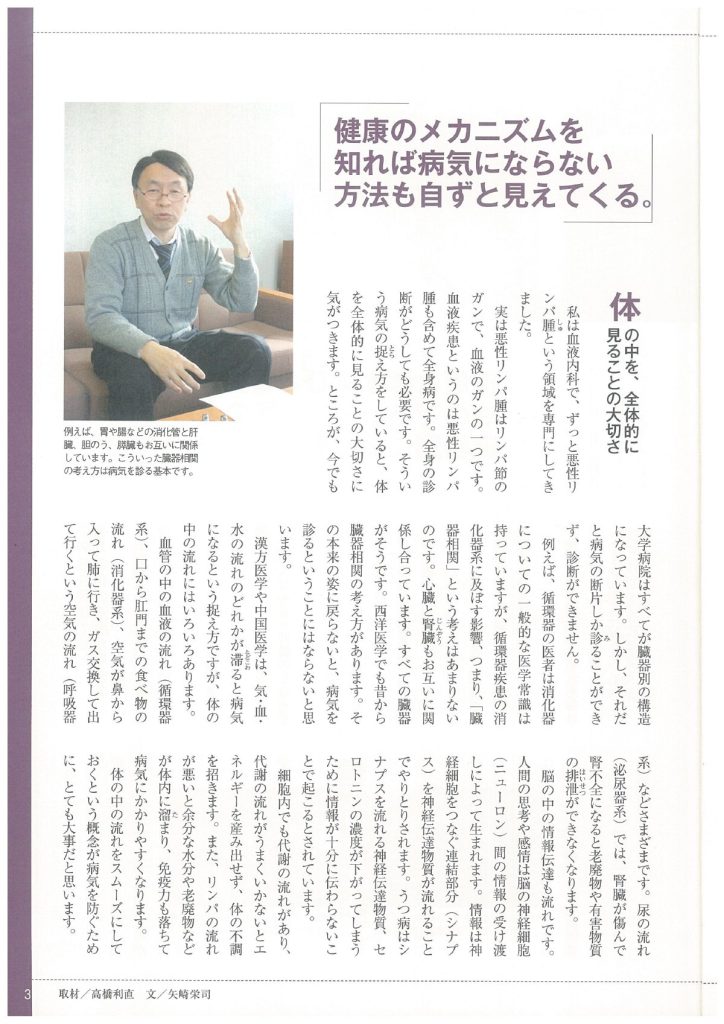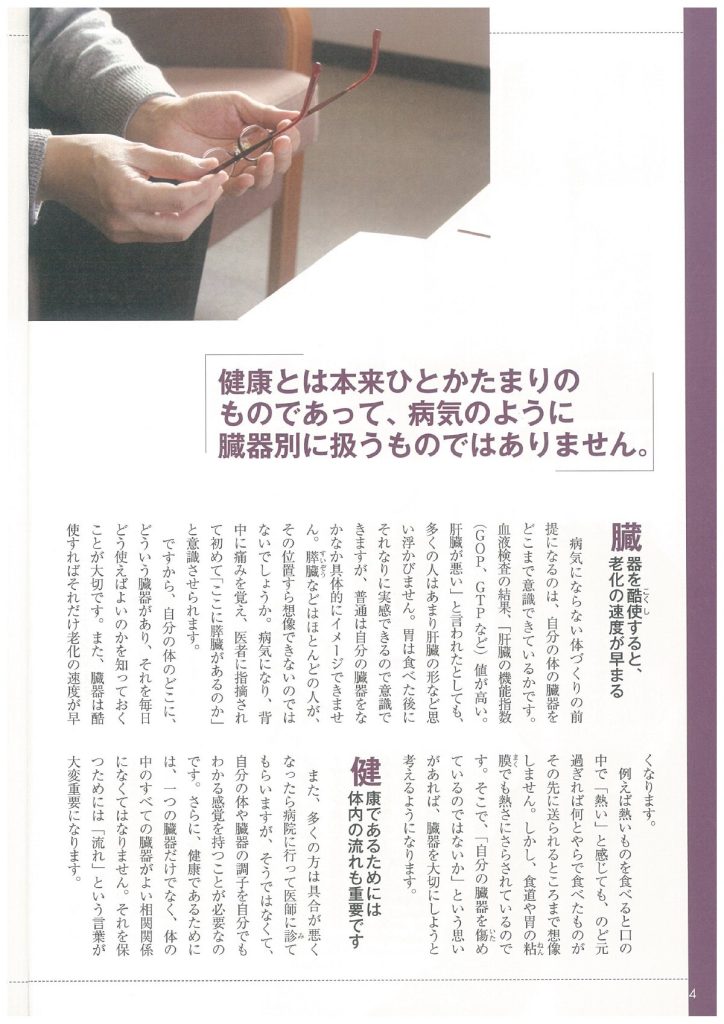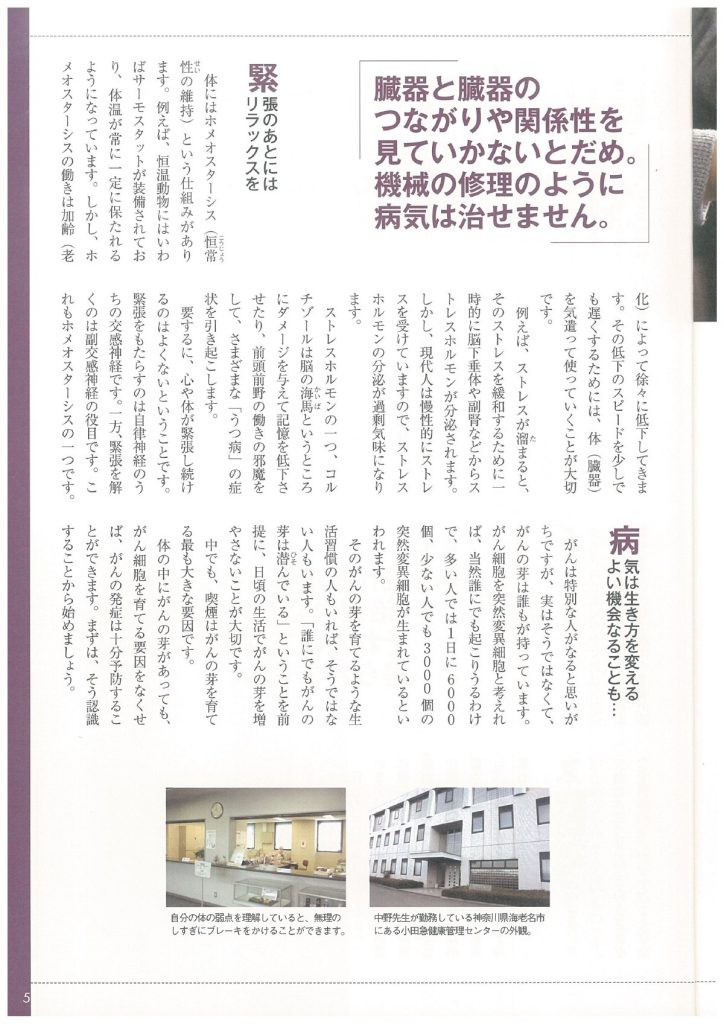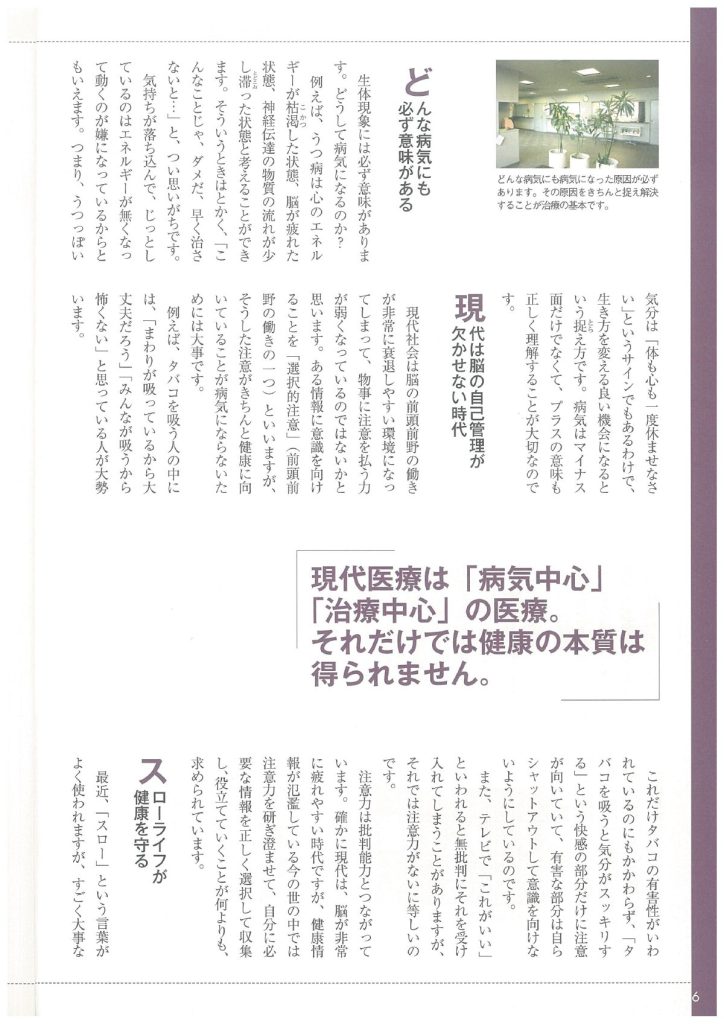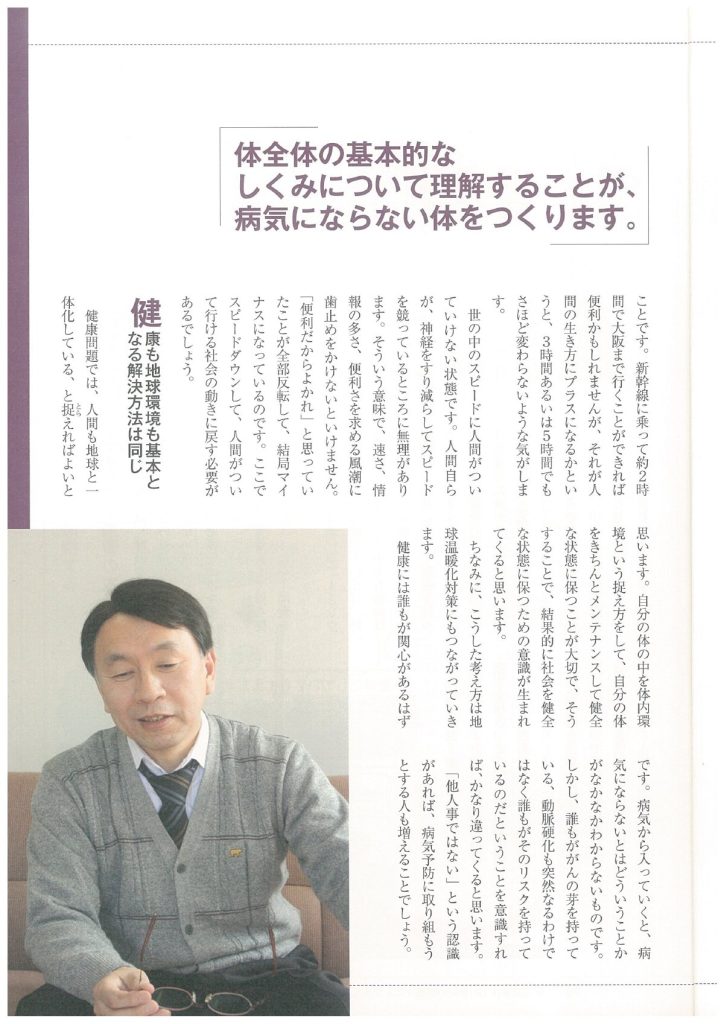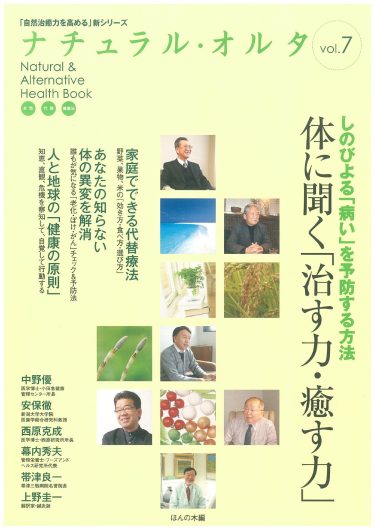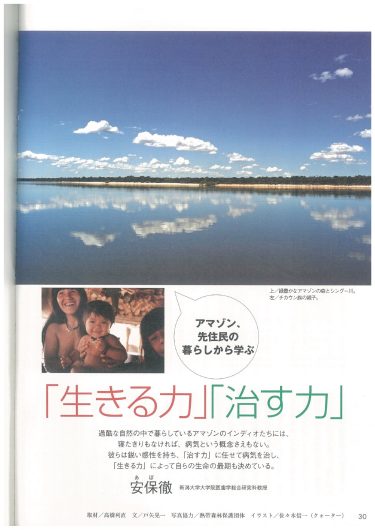病気にならない体づくりの実践
今、人間の体に何が起きているのか?
今でも大学病院では臓器別の構造になっている。しかし、それでは病気の断片しか診ることができないと中野先生は指摘します。体を全体的に捉える視点から、臓器相関(臓器同士の機能的なつながり)のしくみと健康のメカニズムを知ることで、病気にならない体のしくみを理解する大切さについてお聞きしました。
健康のメカニズムを知れば病気にならない方法も自ずと見えてくる。
体の中を、全体的に見ることの大切さ
私は血液内科で、ずっと悪性リンパ腫という領域を専門にしてきました。
実は悪性リンパ腫はリンパ節のガンで、血液のガンの1つです。血液疾患というのは悪性リンパ腫も含めて全身病です。全身の診断がどうしても必要です。そういう病気の捉え方をしていると、体を全体的に見ることの大切さに気がつきます。ところが、今でも大学病院はすべてが臓器別の構造になっています。しかし、それだと病気の断片しか診ることができず、診断ができません。
例えば、循環器の医者は消化器についての一般的な医学常識は持っていますが、循環器疾患の消化器系に及ぼす影響、つまり、「臓器相関」という考えはあまりないのです。心臓と腎臓もお互いに関係し合っています。すべての臓器がそうです。西洋医学でも昔から臓器相関の考え方があります。その本来の姿に戻らないと、病気を診るということにはならないと思います。
漢方医学や中国医学は、気・血・水の流れのどれかが滞ると病気になると言う捉え方ですが、体の中の流れにはいろいろあります。
血管の中の血液の流れ(循環器系)、口から肛門までの食べ物の流れ(消化器系)、空気が鼻から入って肺に行き、ガス交換して出て行くという空気の流れ(呼吸器系)などさまざまです。尿の流れ(泌尿器系)では、腎臓が傷んで腎不全になると老廃物や有害物質の排泄ができなくなります。
脳の中の情報伝達も流れです。人間の思考や感情は脳の神経細胞(ニューロン)間の情報の受け渡しによって生まれます。情報は神経細胞をつなぐ連結部分(シナプス)を神経伝達物質が流れることでやりとりされます。うつ病はシナプスを流れる神経伝達物質、セロトニンの濃度が下がってしまうために情報が十分に伝わらないことで起こるとされています。
細胞内でも代謝の流れがあり、代謝の流れがうまくいかないとエネルギーを産み出せず、体の不調を招きます。また、リンパの流れが悪いと余分な水分や老廃物などが体内に溜まり、免疫力も落ちて病気にかかりやすくなります。
体の中の流れをスムーズにしておくという概念が病気を防ぐために、とても大事だと思います。
健康とは本来ひとかたまりのものであって、病気のように臓器別に扱うものではありません。
臓器を酷使すると、老化の速度が早まる
病気にならない体づくりの前提になるのは、自分の体の臓器をどこまで意識できているかです。
血液検査の結果、「肝臓の機能指数(GOP、GTP など)値が高い。肝臓が悪い」と言われたとしても、多くの人はあまり肝臓の形など思い浮かびません。胃は食べた後にそれなりに実感できるので意識できますが、普通は自分の臓器をなかなか具体的にイメージできません。膵臓などはほとんどの人が、その位置すら想像できないのではないでしょうか。病気になり、背中に痛みを覚え、医者に指摘されて初めて「ここに膵臓があるのか」と意識させられます。
ですから、自分の体のどこに、どういう臓器があり、それを毎日どう使えばよいのかを知っておくことが大切です。また、臓器は酷使すればそれだけ老化の速度が早くなります。
例えば熱いものを食べると口の中で「熱い」と感じても、のど元過ぎれば何とやらで食べたものがその先に送られるところまで想像しません。しかし、食道や胃の粘膜でも熱さにさらされているのです。そこで、「自分の臓器を傷めているのではないか」という思いがあれば、臓器を大切にしようと考えるようになります。
健康であるためには体内の流れも重要です
また、多くの方は具合が悪くなったら病院に行って医師に診てもらいますが、そうではなくて、自分の体や臓器の調子を自分でもわかる感覚を持つことが必要なのです。さらに、健康であるためには、1つの臓器だけでなく、体の中のすべての臓器がよい相関関係になくてはなりません。それを保つためには「流れ」という言葉が大変重要になります。
臓器と臓器のつながりや関係性を見ていかないとだめ。機械の修理のように病気は治せません。
緊張のあとにはリラックスを
体にはホメオスターシス(恒常性の維持)という仕組みがあります。例えば、恒温動物にはいわばサーモスタットが装備されており、体温が常に一定に保たれるようになっています。しかし、ホメオスターシスの働きは加齢(老化)によって徐々に低下してきます。その低下のスピードを少しでも遅くするためには、体(臓器)を気遣って使っていくことが大切です。
例えば、ストレスが溜まると、そのストレスを緩和するために一時的に脳下垂体や副腎などからストレスホルモンが分泌されます。しかし、現代人は慢性的にストレスを受けていますので、ストレスホルモンの分泌が過剰気味になります。
ストレスホルモンの1つ、コルチゾールは脳の海馬というところにダメージを与えて記憶を低下させたり、前頭前野の働きの邪魔をして、さまざまな「うつ病」の症状を引き起こします。
要するに、心や体が緊張し続けるのはよくないということです。緊張をもたらすのは自律神経のうちの交感神経です。一方、緊張を解くのは副交感神経の役目です。これもホメオスターシスの1つです。
病気は生き方を変えるよい機会なることも…
がんは特別な人がなると思いがちですが、実はそうではなくて、がんの芽は誰もが持っています。がん細胞を突然変異細胞と考えれば、当然誰にでも起こりうるわけで、多い人では1日に6000個、少ない人でも3000個の突然変異細胞が生まれているといわれます。
そのがんの芽を育てるような生活習慣の人もいれば、そうではない人もいます。「誰にでもがんの芽は潜んでいる」ということを前提に、日頃の生活でがんの芽を増やさないことが大切です。
中でも、喫煙はがんの芽を育てる最も大きな要因です。
体の中にがんの芽があっても、がん細胞を育てる要因をなくせば、がんの発症は十分予防することができます。まずは、そう認識することから始めましょう。
現代医療は「病気中心」「治療中心」の医療。それだけでは健康の本質は得られません。
どんな病気にも必ず意味がある
生体現象には必ず意味があります。どうして病気になるのか?
例えば、うつ病は心のエネルギーが枯渇した状態、脳が疲れた状態、神経伝達の物質の流れが少し滞った状態と考えることができます。そういうときはとかく、「こんなことじゃ、ダメだ、早く治さないと…」と、つい思いがちです。
気持ちが落ち込んで、じっとしているのはエネルギーが無くなって動くのが嫌になっているからともいえます。つまり、うつっぽい気分は「体も心も一度休ませなさい」というサインでもあるわけで、生き方を変える良い機会になるという捉え方です。病気はマイナス面だけでなくて、プラスの意味も正しく理解することが大切なのです。
現代は脳の自己管理が欠かせない時代
現代社会は脳の前頭前野の働きが非常に衰退しやすい環境になってしまって、物事に注意を払う力が弱くなっているのではないかと思います。ある情報に意識を向けることを「選択的注意」(前頭前野の働きの1つ)といいますが、そうした注意がきちんと健康に向いていることが病気にならないためには大事です。
例えば、タバコを吸う人の中には、「まわりが吸っているから大丈夫だろう」「みんなが吸うから怖くない」と思っている人が大勢います。
これだけタバコの有害性がいわれているのにもかかわらず、「タバコを吸うと気分がスッキリする」という快感の部分だけに注意が向いていて、有害な部分は自らシャットアウトして意識を向けないようにしているのです。
また、テレビで「これがいい」といわれると無批判にそれを受け入れてしまうことがありますが、それでは注意力がないに等しいのです。
注意力は批判能力とつながっています。確かに現代は、脳が非常に疲れやすい時代ですが、健康情報が氾濫している今の世の中では注意力を研ぎ澄ませて、自分に必要な情報を正しく選択して収集し、役立てていくことが何よりも、求められています。
スローライフが健康を守る
最近、「スロー」という言葉がよく使われますが、すごく大事なことです。
体全体の基本的なしくみについて理解することが、病気にならない体をつくります。
新幹線に乗って約2時間で大阪まで行くことができれば便利かもしれませんが、それが人間の生き方にプラスになるかというと、3時間あるいは5時間でもさほど変わらないような気がします。
世の中のスピードに人間がついていけない状態です。人間自らが、神経をすり減らしてスピードを競っているところに無理があります。そういう意味で、速さ、情報の多さ、便利さを求める風潮に歯止めをかけないといけません。「便利だからよかれ」と思っていたことが全部反転して、結局マイナスになっているのです。ここでスピードダウンして、人間がついて行ける社会の動きに戻す必要があるでしょう。
健康も地球環境も基本となる解決方法は同じ
健康問題では、人間も地球と一体化している、と捉えればよいと思います。自分の体の中を体内環境という捉え方をして、自分の体をきちんとメンテナンスして健全な状態に保つことが大切で、そうすることで、結果的に社会を健全な状態に保つための意識が生まれてくると思います。
ちなみに、こうした考え方は地球温暖化対策にもつながっていきます。
健康には誰もが関心があるはずです。病気から入っていくと、病気にならないとはどういうことかがなかなかわからないものです。しかし、誰もががんの芽を持っている、動脈硬化も突然なるわけではなく誰もがそのリスクを持っているのだということを意識すれば、かなり違ってくると思います。「他人事ではない」という認識があれば、病気予防に取り組もうとする人も増えることでしょう。
著者情報
中野優
1950年埼玉県生まれ。東京医科大学大学院終了。医学博士。同大血液内科講師、同大総合健診センター助教授、日本大学医学部非常勤講師、日本血液学会、日本臨床血液学会、日本臨床免疫学会、日本リンパ網内系学会等の評議員を経て、現在小田急電鉄株式会社小田急健康管理センター所長。
クレジット
取材/高橋利直
文/矢崎栄司
(『「自然治癒力を高める」新シリーズ「ナチュラル・オルタナティブ」ヘルスブック⑦ しのびよる「病い」を予防する方法 体に聞く「治す力・癒す力」』より抜粋)
健康やり直し倶楽部 〜健康の新しい扉を開くPodcast〜
「健康やり直し倶楽部」は、健康と心身の調和をテーマに、高橋編集長と川村氏が雑誌「ナチュラル&オルタネイティブ・ヘルスブック」をもとにお届けするPodcast番組です。自然治癒力を引き出す食事やライフスタイル、心の健康、西洋医学と代替医療の融合まで、あらゆる角度から健康を見つめ直します。エピソードで紹介した特集記事をPDFで公開中!新しい知識と実践で、より豊かな生活を始めてみませんか?