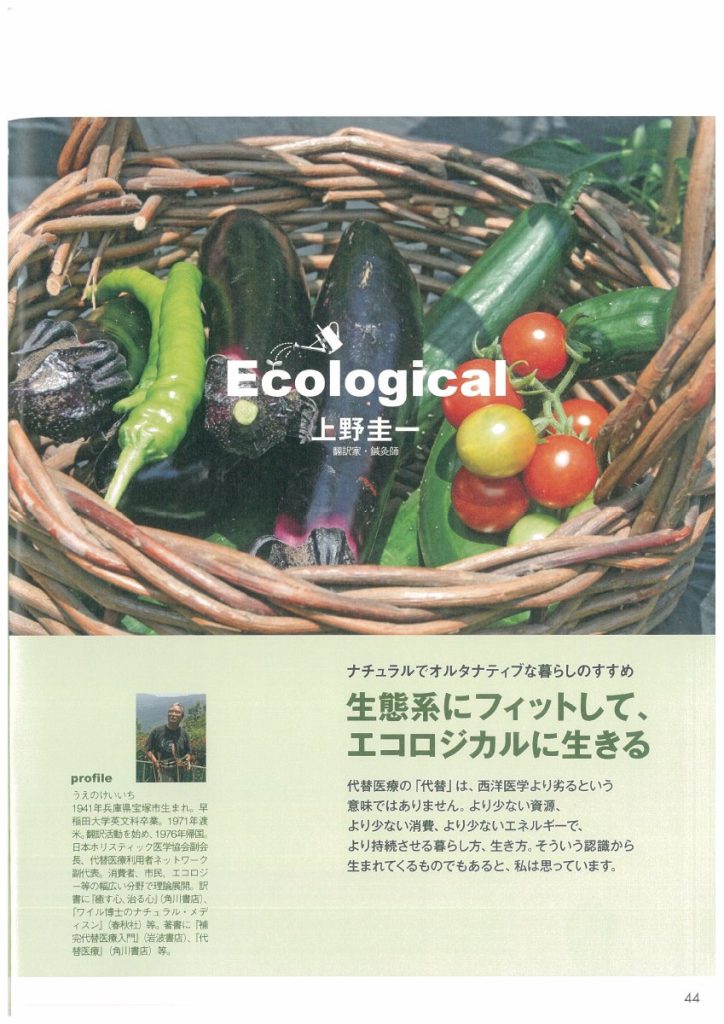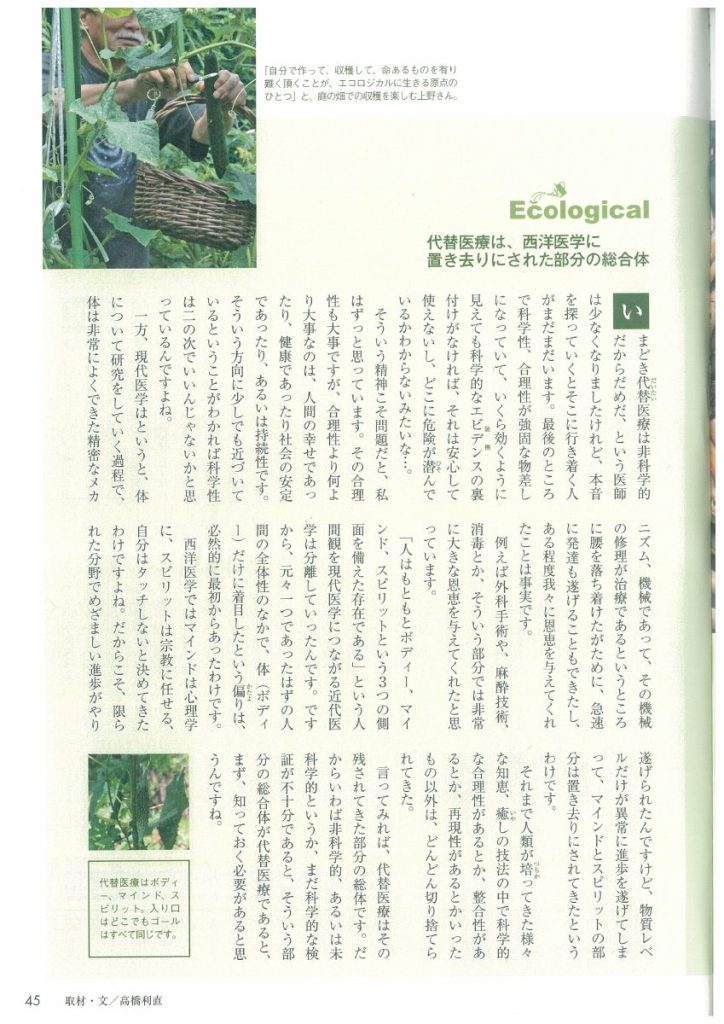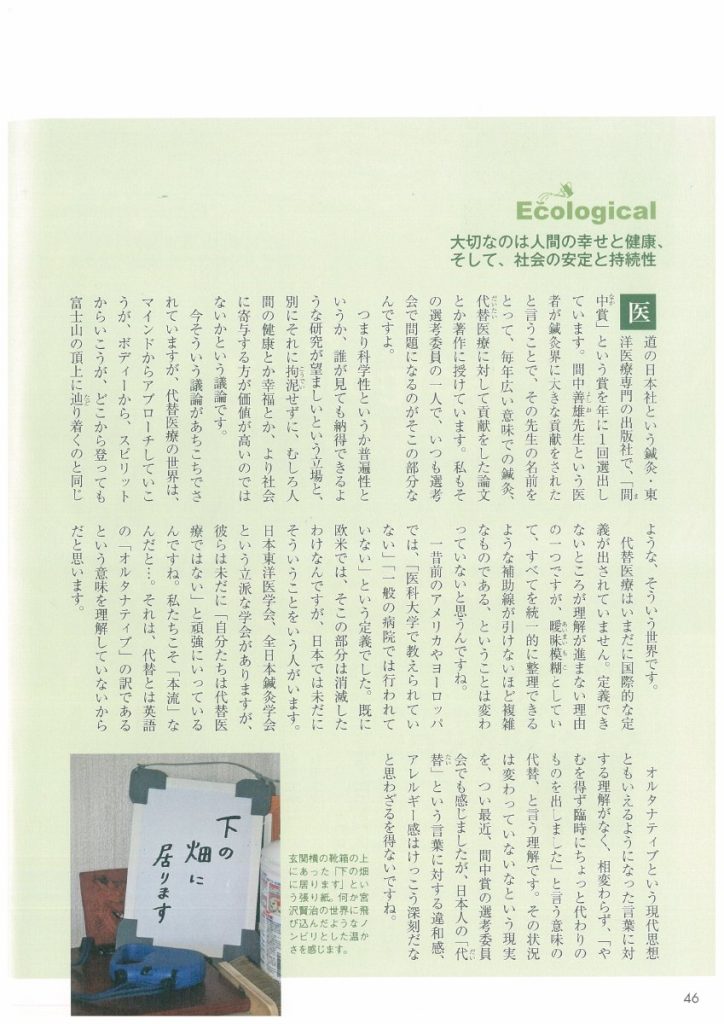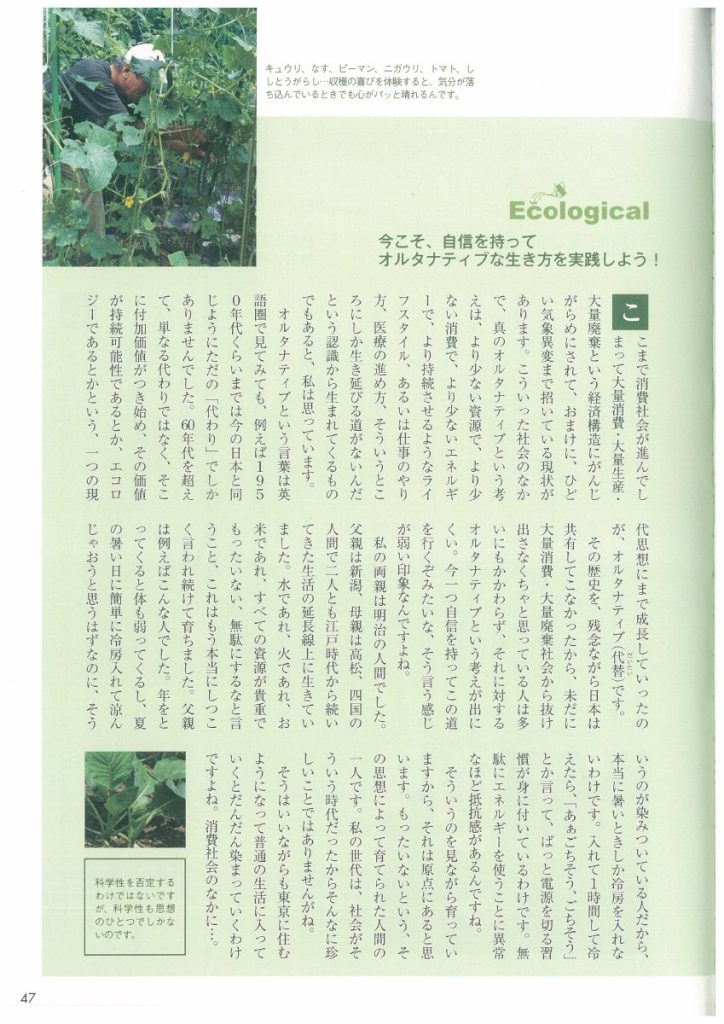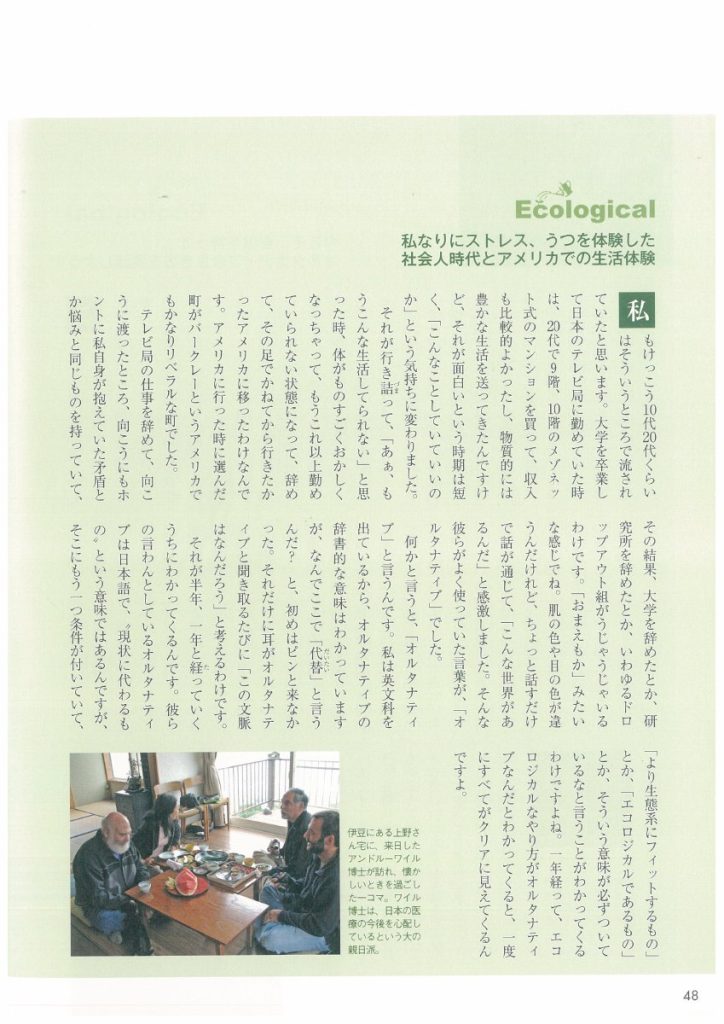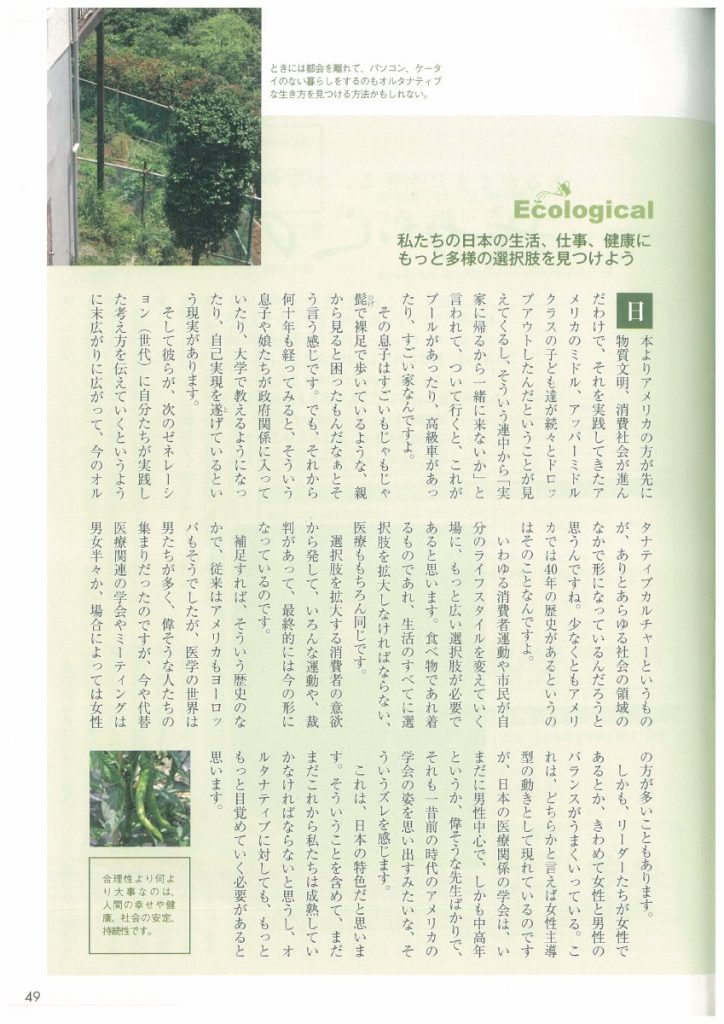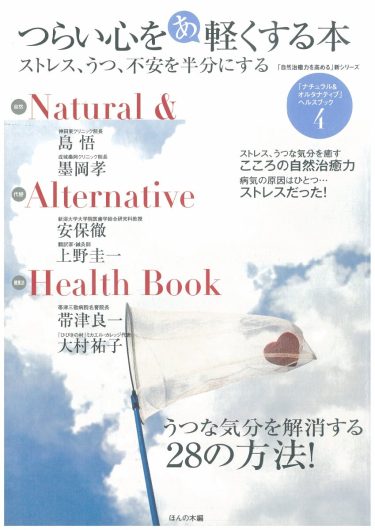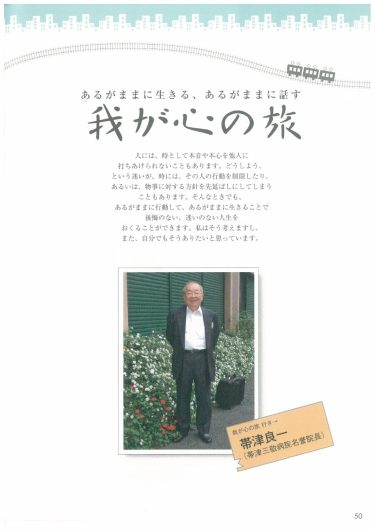ナチュラルでオルタナティブな暮らしのすすめ
生態系にフィットして、エコロジカルに生きる
上野 圭一
翻訳家・鍼灸師
代替医療の「代替」は、西洋医学より劣るという意味ではありません。より少ない資源、より少ない消費、より少ないエネルギーで、より持続させる暮らし方、生き方。そういう認識から生まれてくるものでもあると、私は思っています。
代替医療は、西洋医学に置き去りにされた部分の総合体
いまだ代替医療は非科学的だからだめだ、という医師は少なくなりましたけれど、本音を探っていくとそこに行き着く人がまだまだいます。最後のところで科学性、合理性が強固な物差しになっていて、いくら効くように見えても科学的なエビデンスの裏付けがなければ、それは安心して使えないし、どこに危険が潜んでいるかわからないみたいな…。
そういう精神こそ問題だと、私はずっと思っています。その合理性も大事ですが、合理性より何より大事なのは、人間の幸せであったり、健康であったり社会の安定であったり、あるいは持続性です。そういう方向に少しでも近づいているということがわかれば科学性は二の次でいいんじゃないかと思っているんですよね。
一方、現代医学はというと、体について研究をしていく過程で、体は非常によくできた精密なメカニズム、機械であって、その機械の修理が治療であるというところに腰を落ち着けたがために、急速に発達も遂げることもできたし、ある程度我々に恩恵を与えてくれたことは事実です。
例えば外科手術や、麻酔技術、消毒とか、そういう部分では非常に大きな恩恵を与えてくれたと思っています。
「人はもともとボディー、マインド、スピリットという3つの側面を備えた存在である」という人間観を現代医学につながる近代医学は分離していったんです。ですから、元々1つであったはずの人間の全体性のなかで、体(ボディー)だけに着目したという偏りは、必然的に最初からあったわけです。
西洋医学ではマインドは心理学に、スピリットは宗教に任せる、自分はタッチしないと決めてきたわけですよね。だからこそ、限られた分野でめざましい進歩がやり遂げられたんですけど、物質レベルだけが異常に進歩を遂げてしまって、マインドとスピリットの部分は置き去りにされてきたというわけです。
それまで人類が培ってきた様々な知恵、癒しの技法の中で科学的な合理性があるとか、整合性があるとか、再現性があるとかいったもの以外は、どんどん切り捨てられてきた。
言ってみれば、代替医療はその残されてきた部分の総体です。だからいわば非科学的、あるいは未科学的というか、まだ科学的な検証が不十分であると、そういう部分の総合体が代替医療であると、まず、知っておく必要があると思うんですね。
大切なのは人間の幸せと健康、そして、社会の安定と持続性
医道の日本社という鍼灸・東洋医療専門の出版社で、「間中賞」という賞を年に1回選出しています。間中善雄先生という医者が鍼灸界に大きな貢献をされたと言うことで、その先生の名前をとって、毎年広い意味での鍼灸、代替医療に対して貢献をした論文とか著作に授けています。私もその選考委員の一人で、いつも選考会で問題になるのがそこの部分なんですよ。
つまり科学性というか普遍性というか、誰が見ても納得できるような研究が望ましいという立場と、別にそれに拘泥せずに、むしろ人間の健康とか幸福とか、より社会に寄与する方が価値が高いのではないかという議論です。
今そういう議論があちこちでされていますが、代替医療の世界は、マインドからアプローチしていこうが、ボディーから、スピリットからいこうが、どこから登っても富士山の頂上に辿り着くのと同じような、そういう世界です。
代替医療はいまだに国際的な定義が出されていません。定義できないところが理解が進まない理由の1つですが、曖昧模糊としていて、すべてを統一的に整理できるような補助線が引けないほど複雑なものである、ということは変わっていないと思うんですね。
一昔前のアメリカやヨーロッパでは、「医科大学で教えられていない」「一般の病院では行われていない」という定義でした。既に欧米では、そこの部分は消滅したわけなんですが、日本では未だにそういうことをいう人がいます。日本東洋医学会、全日本鍼灸学会という立派な学会がありますが、彼らは未だに「自分たちは代替医療ではない」と頑強にいっているんですね。私たちこそ「本流」なんだと…。それは、代替とは英語の「オルタナティブ」の訳であるという意味を理解していないからだと思います。
オルタナティブという現代思想ともいえるようになった言葉に対する理解がなく、相変わらず、「やむを得ず臨時にちょっと代わりのものを出しました」と言う意味の代替、と言う理解です。その状況は変わっていないなという現実を、つい最近、間中賞の選考委員会でも感じましたが、日本人の「代替」という言葉に対する違和感、アレルギー感はけっこう深刻だなと思わざるを得ないですね。
今こそ、自信を持ってオルタナティブな生き方を実践しよう!
ここまで消費社会が進んでしまって大量消費・大量生産・大量廃棄という経済構造にがんじがらめにされて、おまけに、ひどい気象異変まで招いている現状があります。こういった社会のなかで、真のオルタナティブという考えは、より少ない資源で、より少ない消費で、より少ないエネルギーで、より持続させるようなライフスタイル、あるいは仕事のやり方、医療の進め方、そういうところにしか生き延びる道がないんだという認識から生まれてくるものでもあると、私は思っています。
オルタナティブという言葉は英語圏で見てみても、例えば1950年代くらいまでは今の日本と同じようにただの「代わり」でしかありませんでした。60年代を超えて、単なる代わりではなく、そこに付加価値がつき始め、その価値が持続可能性であるとか、エコロジーであるとかという、1つの現代思想にまで成長していったのが、オルタナティブ(代替)です。
その歴史を、残念ながら日本は共有してこなかったから、未だに大量消費・大量廃棄社会から抜け出さなくちゃと思っている人は多いにもかかわらず、それに対するオルタナティブという考えが出にくい。今1つ自信を持ってこの道を行くぞみたいな、そう言う感じが弱い印象なんですよね。
私の両親は明治の人間でした。父親は新潟、母親は高松、四国の人間で二人とも江戸時代から続いてきた生活の延長線上に生きていました。水であれ、火であれ、お米であれ、すべての資源が貴重でもったいない、無駄にするなと言うこと、これはもう本当にしつこく言われ続けて育ちました。父親は例えばこんな人でした。年をとってくると体も弱ってくるし、夏の暑い日に簡単に冷房入れて涼んじゃおうと思うはずなのに、そういうのが染みついている人だから、本当に暑いときしか冷房を入れないわけです。入れて1時間して冷えたら、「あぁごちそう、ごちそう」とか言って、ぱっと電源を切る習慣が身に付いているわけです。無駄にエネルギーを使うことに異常なほど抵抗感があるんですね。
そういうのを見ながら育っていますから、それは原点にあると思います。もったいないという、その思想によって育てられた人間の一人です。私の世代は、社会がそういう時代だったからそんなに珍しいことではありませんがね。
そうはいいながらも東京に住むようになって普通の生活に入っていくとだんだん染まっていくわけですよね。消費社会のなかに…。
私なりにストレス、うつを体験した社会人時代とアメリカでの生活体験
私もけっこう10代20代くらいはそういうところで流されていたと思います。大学を卒業して日本のテレビ局に勤めていた時は、20代で9階、10階のメゾネット式のマンションを買って、収入も比較的よかったし、物質的には豊かな生活を送ってきたんですけど、それが面白いという時期は短く、「こんなことしていていいのか」という気持ちに変わりました。
それが行き詰って、「あぁ、もうこんな生活してられない」と思った時、体がものすごくおかしくなっちゃって、もうこれ以上勤めていられない状態になって、辞めて、その足でかねてから行きたかったアメリカに移ったわけなんです。アメリカに行った時に選んだ町がバークレーというアメリカでもかなりリベラルな町でした。
テレビ局の仕事を辞めて、向こうに渡ったところ、向こうにもホントに私自身が抱えていた矛盾とか悩みと同じものを持っていて、その結果、大学を辞めたとか、研究所を辞めたとか、いわゆるドロップアウト組がうじゃうじゃいるわけです。「おまえもか」みたいな感じでね。肌の色や目の色が違うんだけれど、ちょっと話すだけで話が通じて、「こんな世界があるんだ」と感激しました。そんな彼らがよく使っていた言葉が、「オルタナティブ」でした。
何かと言うと、「オルタナティブ」と言うんです。私は英文科を出ているから、オルタナティブの辞書的な意味はわかっていますが、なんでここで「代替」と言うんだ?と、初めはピンと来なかった。それだけに耳がオルタナティブと聞き取るたびに「この文脈はなんだろう」と考えるわけです。
それが半年、一年と経っていくうちにわかってくるんです。彼らの言わんとしているオルタナティブは日本語で、「現状に代わるもの」という意味ではあるんですが、そこにもう1つ条件が付いていて、「より生態系にフィットするもの」とか、「エコロジカルであるもの」とか、そういう意味が必ずついているなと言うことがわかってくるわけですよね。一年経って、エコロジカルなやり方がオルタナティブなんだとわかってくると、一度にすべてがクリアに見えてくるんですよ。
私たちの日本の生活、仕事、健康にもっと多様の選択肢を見つけよう
日本よりアメリカの方が先に物質文明、消費社会が進んだわけで、それを実践してきたアメリカのミドル、アッパーミドルクラスの子ども達が続々とドロップアウトしたんだということが見えてくるし、そういう連中から「実家に帰るから一緒に来ないか」と言われて、ついて行くと、これがプールがあったり、高級車があったり、すごい家なんですよ。
その息子はすごいもじゃもじゃ髭で裸足で歩いているような、親から見ると困ったもんだなぁとそう言う感じです。でも、それから何十年も経ってみると、そういう息子や娘たちが政府関係に入っていたり、大学で教えるようになったり、自己実現を遂げているという現実があります。
そして彼らが、次のゼネレーション(世代)に自分たちが実践した考え方を伝えていくというように末広がりに広がって、今のオルタナティブカルチャーというものが、ありとあらゆる社会の領域のなかで形になっているんだろうと思うんですね。少なくともアメリカでは40年の歴史があるというのはそのことなんですよ。
いわゆる消費者運動や市民が自分のライフスタイルを変えていく場に、もっと広い選択肢が必要であると思います。食べ物であれ着るものであれ、生活のすべてに選択肢を拡大しなければならない、医療ももちろん同じです。
選択肢を拡大する消費者の意欲から発して、いろんな運動や、裁判があって、最終的には今の形になっているのです。
補足すれば、そういう歴史のなかで、従来はアメリカもヨーロッパもそうでしたが、医学の世界は男たちが多く、偉そうな人たちの集まりだったのですが、今や代替医療関連の学会やミーティングは男女半々か、場合によっては女性の方が多いこともあります。
しかも、リーダーたちが女性であるとか、きわめて女性と男性のバランスがうまくいっている。これは、どちらかと言えば女性主導型の動きとして現れているのですが、日本の医療関係の学会は、いまだに男性中心で、しかも中高年というか、偉そうな先生ばかりで、それも一昔前の時代のアメリカの学会の姿を思い出すみたいな、そういうズレを感じます。
これは、日本の特色だと思います。そういうことを含めて、まだまだこれから私たちは成熟していかなければならないと思うし、オルタナティブに対しても、もっともっと目覚めていく必要があると思います。
著者情報
上野 圭一
1941年兵庫県宝塚市生まれ。早稲田大学英文科卒業。1971年渡米。翻訳活動を始め、1976年帰国。日本ホリスティック医学協会副会長、代替医療利用者ネットワーク副代表。消費者、市民、エコロジー等の幅広い分野で理論展開。
クレジット
取材・文/高橋利直
(『「自然治癒力を高める」新シリーズ「ナチュラル・オルタナティブ」ヘルスブック④ つらい心をあ軽くする本』より抜粋)
健康やり直し倶楽部 〜健康の新しい扉を開くPodcast〜
「健康やり直し倶楽部」は、健康と心身の調和をテーマに、高橋編集長と川村氏が雑誌「ナチュラル&オルタネイティブ・ヘルスブック」をもとにお届けするPodcast番組です。自然治癒力を引き出す食事やライフスタイル、心の健康、西洋医学と代替医療の融合まで、あらゆる角度から健康を見つめ直します。エピソードで紹介した特集記事をPDFで公開中!新しい知識と実践で、より豊かな生活を始めてみませんか?