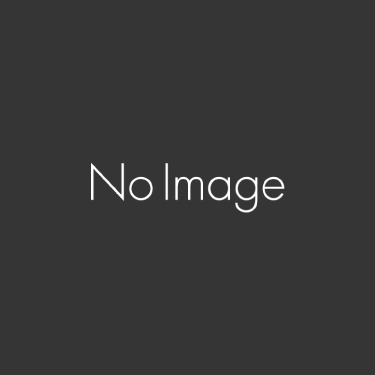多忙な教員たち
教員の忙しさが問題になって久しくなります。「忙しい」とは、文字通り、「心が亡くなること」。「心が亡くなる」とは、自分がしていることの意味をじっくり考えるゆとりがなくなってしまっている状態のことを言っています。
実際、これまでに数回、自治体の校長研修や教員研修、また、大学での特別講義に出かけたことがありますが、講演中に少なくない数の先生が居眠りを始めるのは例外ではありません。一度、オランダの有名な教育学の教授を招いて日本でシンポジウムをしたとき、会場で聞いている人が居眠りをして、教授がカンカンに怒ったことがありました。
オランダでは、研修会の参加者や大学で講義を受けている学生がその場で眠るという光景に出くわすことはまずありません。おそらく、会場の視聴者は、あたかもテレビの番組でもみているような気持ちなのかもしれませんが、血の通った心のある講演者にとって、会場で「眠る」ほど不遜な態度はないのです。
そもそも、自治体が住民から集めた税金を使って雇っている先生や校長先生たちが、研修会で「居眠り」をするなんて、住民にしてみれば、ありえないこと、あってはならないことではないでしょうか。でも、よくよく話を聞いてみると、校長会や教職員の研修会に出られる先生たちは、毎日の過密なスケジュールの合間を縫って、または、毎日早朝から忙しい仕事をしていて、疲労が蓄積している、眠るつもりはないのについうとうと、と言うのが現状のようでした。
確かに学校という場所は、職員にたくさんの仕事をもたらしている場所なのかもしれません。毎日の授業の準備、授業中の指導、採点や評価、さまざまな質問や苦情を持つ保護者への対応、職員会議や専門分野に関する委員会会議、催し物や行事の準備、放課後に生徒たちが起こす問題の処理、いじめや不登校の対策、生活指導、特別な学習障害を持つ子どもへの対応、さらに部活指導まであっては、本当にホッと息をつく間もない忙しさだというのは、容易に想像できます。
現に、疲れ切った先生、燃え尽き症候群に苦しんでいる先生に指導されている子どもたちのことを考えると、ことは深刻です。でも、かといって、「では、先生の仕事を軽減しましょう」と事務仕事の簡易化・効率化や、教員としては副次的だと思われる仕事を他の人に委任することだけで、問題は解決できるものなのでしょうか?
私は、先生方の慢性的な疲れの後ろには、何か、もっと根源的なものがあるような気がしてならないのです。それは、教育者として、教育そのものに自分がコミットできないでいること、自分の仕事を教育者として誇れる内容のものにしたくてもできないことにあるように感じます。
学校の先生の大半は、かつて、「学校の先生になろう」と思った時に、子どもたちの育ちに関わりたい、次世代を背負っていく人たちの発達に貢献したい、という輝かしい志を心のどこかに抱いていたのではないでしょうか。しかし、先生たちのそうした初心を徐々に失わせるような、子どもの成長に自分なりにアクティブにコミットしていくという働き方がしづらい状況が、学校の中で当たり前になってしまっていることに、深い疲れの原因があるのではないのでしょうか。
学校に、”人間”である教員がいることの意味
コロナの感染の広がりによって、昨年以来、休校が増え、オンラインでの授業がグッと増えました。オンライン授業やデジタル教材の普及により、学力面では、子どもたちそれぞれの発達のレベルに合わせた学び方も可能になっていると思います。
しかし同時に、こうした事態は、学校という物理的な場所に子どもたちが毎日集まってくる意味、そこに、先生がいて、子どもたち一人一人の様子を観察し、声をかけ、見守ってくれることの意味を、改めて考えるきっかけになったのではないかとも思います。学校は、子どもたちの認知的能力(教科ごとの学力的な能力)だけではなく、社会性や情緒の発達にも深く関わっている場所だと言うことへの気づきです。
人間としての子どもが、社会性を発達させ、情緒のコントロールを学んでいくためには、どうしてもその場に他の子どもたちがいて、それを安全や安心を保証しながら見守り、必要に応じて声をかけたり、危ないことやしてはいけないことをきちんと伝える、「人間」としての経験と感覚を持った先生が必要です。
コンピューターが読み取れる子どもたちの様子以外の情報をキャッチできる種々の感覚を備えた「人間」としての教員です。それは、母親が、朝、寝床から起きてきた子どもの様子から、「ちょっと具合が悪いのかな」と察知する能力にも似ています。いつもの様子と違う、元気がなさそうだ、悲しそうな表情をしている、興奮している、怒っている、そうした子どもの様子を読み取り、子どもの声に耳を傾け、安心の場を与え、その子のニーズがなんなのかを判断し、ふさわしい言葉がけや課題をふさわしい時に与えて、その子の発達を支援する…。それが先生の仕事です。
本来「先生になりたい」と思った先生たちの初心の底には、自分が、独立した「人間として」自分の経験や感覚を使って若い人たちの成長に寄与することができるという志があったはずなのです。
初心に戻るために「なぜ」を語り合う
教員たちに、この初心、志を忘れさせ、あるいは、この初心を夢物語のように感じさせてしまうものは、なんなのでしょう。教員としての「理想」の旗を降ろさせてしまうものはなんなのでしょうか。学校の先生たちが、この初心に戻ることができ、「理想」を語れるようにするには、どうすれば良いのでしょう?
わたしは、それは、大人たちが「なぜ」に立ち返ること、「なぜ」と問い返す心の自由を取り戻すこと、お互いに自分の意思や判断で仕事を進める自由を尊重し合うことであると思っています。でも、そのためには、「自分勝手」ではなく、「対話」を通して常にお互いに対して意見を言い合い、自分に反対する人の意見を受け入れ合う関係を生み出していくことが大切です。
「わたし(たち)は、なぜ今これをしているのか」「わたし(たち)は、なぜ、この方法を選んだのか」「わたしが、これをし、この方法を選ぶことは、なぜ子どもたちにとって意味があるのか」と問い続け、意見を交換し合う状態を継続して維持していくことです。
管理文化が支配的な学校には、学校の職員間の交流すらなくなってしまっています。
グレーのスチール机に、あたかも砦を築くように堆く積み上げた書類、書類の後ろに隠れて、同僚とは言葉を交わすこともなく仕事をしている教員たち。そういう職員室に一度ならず心が塞がる思いをしました。喫茶室のようにリラックスでき、コーヒーカップを片手に同僚と気楽におしゃべりができるオランダの職員室とあまりに違っているからです。
ここには、「なぜ(Why)」を語り合う、つまり、自分は「子どもたちの成長にどう関わろうとしているのか」という、教員たちが、心の底に深く抱いている想いや迷いを語り合う雰囲気は感じられません。
「何をするか(What)」「どんなふうにするか(How)」ももちろん大切です。つまり、いつ(When)、誰(Who)に、何(What)を教えなければならないか、それをどんな教材や授業の形で実施するか(How,Which)、ということです。
でも、ここには「なぜ(Why)」がありません。教え導くことの意義、それは、本当はこの「なぜ(why)」 を抜きにしては考えられないことであるはずなのに、です。
教員たち(教育の専門家たち)が、そこで「なぜこれなのか」「なぜこの方法なのか」「なぜ今なのか」「なぜここでそれをするのか」と考える時、そこに、一人ひとりの子どもの姿、それを観察している教員たちのありとあらゆる感覚の重要性が立ち上がってきます。
「なぜ」を語り合う学校共同体の大切さ
教員たちを管理するためのさまざまな事務仕事、管理下に置かれて自分の意思で自由に判断することができなくなってしまった教員たちへの保護者の不満、そこから起きてくるさまざまな苦情とその処理、教員同士の信頼感情が薄いために「誰かに委任すること」「一緒に働くこと」をできなくさせ、そのために起きてしまう効率の悪さ…。
こうしたことは、実は、管理体制が強ければ強くなるほど起こることのように感じています。本来学校における「管理」は、子どもたちに安心・安全の場を提供することが目的であったはずなのに、実は、その「管理」のために、教員同士が語り合う機会が奪われ不信が広がる、教員と保護者の間で情報交換ができず不信や対立が起こる、また、このようにして不信感が支配してしまった学校で、子どもたちが安心感を得られず、学校嫌いになったり不登校になったりする…。そういう悪循環が広がっているように見えます。
でも、学校という同じ場所で、同じ子どもたちと毎日関わっている教員や保護者という大人集団が、「なぜ」と語り合い、お互いの視点から学び合うという文化を生み出して行けたらどうでしょう?
管理体制の中では、一人一人の教員は自分の判断で裁量する自由を感じることができません。全てを、まずは「規則」に照らし、規則がなければ「慣習」に照らして自分の行為を決定します。その結果、うまくいかなかったときにも、自分で「責任」を取りたいと感じることができないのです。教員たちの仕事から「心」を奪っているのは、管理による運営そのものなのです。
自分たちが「なぜ」と批判的に考える自由を与えられ、自分たちの中から、本当に大切なものはなんで、あまり大切ではないものはなんなのか、と優先順位を決定したり、協力して何かの取り組みをしようという動きが出て来れば、たとえ失敗しても、その失敗から一緒に学ぼうという心の動きが出てくるのではないでしょうか。
学校が「独立」した「共同体」でなければならない理由はここにあるのです。
まずは大人が遊び、催すこと
でも、ここで一つ、大きな大きな落とし穴があります。
今まで、自分たち自身が、伝統的な画一一斉授業の中で受け身に学んできた日本の大人の大半は、自分の考えを言葉にして表す練習をしてこなかったし、誰か他の人から「なぜ」と問われる経験も少なかったことと思います。大人たち自身が、誰か他の人に自分の気持ちを率直に正確に伝える練習をしてきていないのです。
管理教育の中で、教員の指示することに従いながら学んできた大人たちには、自己肯定感を育てるゆとりも少なかったと思います。ましてや、自分が話す練習をしたことがない人に、人の話にしっかり耳をかた向けるゆとりなどあるはずもありません。
保育園に通っているような小さい子どもの時から、「嫌なことにはノーと言っていいのだ」と教えられ、自分の感情を「言葉で言い表すように」と促されてきたオランダ人とは違い、とかく「他者に合わせること」「出る杭にならないこと」を学び身につけた大人たちにとって、誰かの意見に反対すること、また、誰かから反対されることは、必要以上にネガティブな感情を引き出してしまうようです。
日本人の会話によくある、他の人の発言に「うなづく」「そうそう」と相槌を打つ、といった態度は、それをみている人にとって、ますますその人たちとは違う意見を言いにくくしているとも思います。そういう状態にある、つまり、「違っていてもいいんだよ」ということを心底確信できていない大人たちに対して是非わたしが勧めたいのは、子どもたちと同じように、まずは、大人同士、まずはしっかり遊び、催しの中で共感を育むことです。
校長であるとか、クラス担任の新任教員であるとか、先輩・後輩という序列づけに拘らず、お互いを一人のオールラウンドの人間として受け入れ合い、人として平等に関わり合うための練習の場です。そのために一緒に遊んだり、一緒に何かを催す時間をまず設けてほしいのです。
若い新任の先生が、校長先生や保護者も一緒に、サッカーを教える。手芸の好きな年配の先生が、他の職員や保護者を集めて手芸教室を開く。ディスコの夕べを開いてみんなで踊り明かす。校長先生も保護者も地域の人も一緒になって、笑い転げながらパン食い競争をやる…。
また、お互いの誕生日には、短くても必ずみんなで一緒にお祝いの言葉を述べ合う。職員や保護者の家族に病気や誰かの死など不幸があったときには、共に苦しみを分かち合う。こうした時間が、学校に関わる大人たちの信頼感情を深め、「この学校があってよかった」と思える、心地よい「村」に帰るような気分が生み出せたらどうでしょう。できれば、お互いに「ノー」と言い合う練習もすると良いと思います。「◯◯が好きな人、嫌いな人?」という、ごく身近ななんでもないことを使って「ノー」と言い合える習慣を生み出していくのです。違いを受け入れ、違いこそが社会の豊かさであることを実感するためです。
学校教育のさまざまな「なぜ」について、本当に建前でではなく、深く本音で語り合えるようになるために、一見回り道のように見えるかもしれませんが、遊び催して信頼関係に根ざしたグループを作り出しておくことは、とても大切なことだと思っています。(続く)