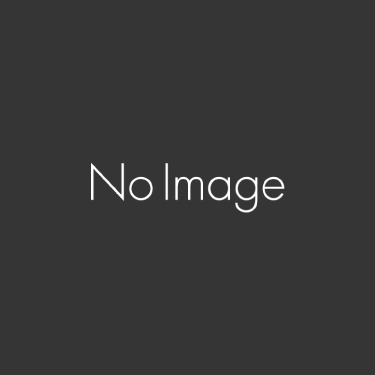人間が生まれつき持っている共感力
オランダの学校で採用されているシチズンシップ教育の教材の中にこんな授業があります。
オランダ人が普段あまり出会うことのない異国の部族の人たちの顔写真を子どもたちに見せて「この写真の中にいるこの人は、今どんな気持ちなんだと思う?」と問いかけるのです。
子どもたちは、自分とは、髪の色も、目の色も、肌の色も、着ている衣服も違う写真の中の人の表情を見て、「嬉しそう」「悲しそう」「何か心配しているのかな」「怒っているみたい」と、口々に言い合います。これは、自分や他の人の感情を言葉で表現するという練習でもあるのですが、それ以上に、見たこともない外見の、文化も宗教も異なる地球の裏の人々の気持ちを、そうやって表情から推し量るように促すことには大変大きな意味があると思います。
もし読者の皆さんにもチャンスがあったら、子どもたちと一緒にコンピューターか携帯電話の画面の前に座り、色々な国の人の写真を、”People in Fiji”とか”People in Senegal”, “People in Peru”というふうに検索して、子どもたちに、その写真の中にいる人たちの表情からどんな気持ちだと受け止めているのか、言葉にして話させてみるといいと思います。
やってみればわかると思いますが、大抵の子どもたちは、写真の中にいる人が、自分が見たことのない異国の人であっても、その人が今どんな気持ちであるかを表情から読み取れるものです。子どもとは、いえ、私たち人間とは、生まれつき、他者への共感力を持った存在なのです。人間は、他者なくしては生きていけない、社会を必要とする存在ですし、共感力もまた、そういう社会的存在としての人間に備えられた力なのだと思います。
幼い時から、地球の裏の人たちとの共感力をこうして養っておくことは、人間への信頼を育む第一歩になると思います。
共感力を萎えさせるもの
けれども、大人たちは、そして学校文化の中にいる大人たちは、そういう、文化や宗教の境界などをまだ知らない、子どもたちが持っている、人としての率直な共感力を、知らず知らずのうちに萎えさせてきたのではないかと思います。
学校に行くと、クラスが分かれる、クラス対抗スポーツデー、紅組・白組に分かれた運動会がある、男女を分ける活動もある、校歌や国歌を歌う、学校対抗試合がある、学校ごとに決まった制服や校章がある、同じ学区内でも、異なる性格を持つ地域では、住民同士が不信感を持つなんてこともありますね。また、自分が住んでいる郷土や国の歴史を学ぶことは、とても大切ではあります。でも、それを、外の人はどう学んでいるのか、外から見ている人たちはどう考えているのかを同時に学んだり考えたりする機会があまりないのは、このグローバル化の時代には、とても残念なことです。オンラインで他地域の学校や外国の学校と交流することの意義は、ここにもあると思います。
ある都市、ある国の市民としての行動様式だけを学ぶのでは済まなくなっているのが今の時代です。今の時代、産業活動も文化活動も政治も経済も、皆、国境を越えずに行われているものはほとんどないと言ってもいいくらいです。また、コロナの感染でも私たち自身、身に沁みて感じた通り、私たちの生存を脅かしている環境破壊や感染病などの問題は、今や、一国の施策だけで解決できるものではなく、他国の人々が積極的に自分ごととして解決のために貢献する態度を持たなくては解決の一歩を踏み出せないものばかりだからです。しかも、今地球が直面している問題は、過去の歴史を紐解いても簡単に解決策を見出すことができない物、人類史上初めての課題も少なくありません。
つまり、「主体的市民」として、自分の頭を駆使して批判的に考え、クリエイティブなアイデアを生み出し、自分とは異なる他者を尊重して、より良い世界のために積極的に社会に参加し貢献する人間を生み出す教育は、その舞台を、小さな地域から、国境を越えた地球社会へと移さなければならない時代を私たちは生きているのです。
そう考えると、これまで、母校愛、スポーツ精神、学校対抗試合、母国愛と、あまりにもどこでも行われていて、学校文化としては空気のように当たり前だったことが、別の意味を持って見えてくるのではないでしょうか。
共感は国境を越えた地球の裏まで
もちろん、私にだって、母校を懐かしむ気持ち、母国を愛する気持ちはあります。でも、その時に感じる懐かしい気持ちは、その土地の風土と繋がった家族や友との共感の思い出だったり、美しい場所に共に立っていたことだったり、何か嬉しいこと苦しいことを一緒に経験した思い出だったり、誰かに慰められたり励まされたりしたことだったりで、みんながそこに集団として集まっていたことを取り立てて懐かしく思うようなものではありません。
また、何か過去に起きたことを他者とともに懐かしく感じるという、思い出や経験の共有は、その後、移り住んだ様々の土地で、そこに住んでいる人たちとも経験したことで、自分の母国の同胞とだけ、母校での同窓生とだけに限られるものとも思えません。
かつて、道徳教育では、「他の人の迷惑にならないように」どう行動すべきかを教えられたものです。そのこと自体は何も間違っていません。でも、そういう徳目を教えながら、同じ教室、同じ学校の中で、グループに分かれて競走したり、スポーツやコーラスや学力を学校対抗で競わせたり、自国の歴史を誇ることばかりを教えたりしているというのは、何か少し矛盾しているのではないでしょうか。今の時代、人間のありとあらゆる活動が、国境を越えた、地球の裏側の人々の生活と関わっているのであれば、その国の人たちは、自分自身がしている行為とどう関わっているのか、その国の人たちは、自分や自分の国の人たちがしていることによって「何か迷惑を被ってはいないのか」と考えるのは、道徳教育の徳目からすると大事な行為であるはずなのです。
たとえば、今飲んでいるコーヒーは、きっと日本ではない遠い土地で作られたものに違いないですが、生産者はどんな生活をしながらコーヒーを作っているのでしょう? コロナの予防注射を急いで買い集め感染を抑えたのは良いけれど、その間に予防注射が不足している国の人たちの健康は誰が守るのでしょう?
道徳教育、それとも、シチズンシップ教育?
道徳教育か、それとも、シチズンシップ教育か、という議論があります。このふたつは、似ているようでいてやっぱり違う、そして、教育者は、そのことをしっかりと自覚して子どもたちと接していかなければならないのではないか、と思っています。なぜなら、道徳教育は、多くの場合、ある土地の固有の文化やそこで信じられている宗教倫理を共有している人たちの間で伝統的に作られてきた行動規範をベースにしていることがほとんどだからです。
でも、シチズンシップ教育は、まさに、そのように、土地土地で異なる規範、宗教の経典によって少しずつ異なる倫理観を乗り越えて、人間としての共通の原理に立ち返ってお互いを受け入れ合う心構えを子どもたちに身につけさせようとするものです。宗教や政治的立場、権力からの影響という境界を乗り越えた、個々の人々の真の自由意志に基づく社会参加を涵養することが、シチズンシップ教育の目的です。
けれどもそれは、自分が生まれ落ち、これまで拠ってきた文化的な規範を「否定」しなければならないというものでも必ずしもありません。なぜなら、多くの文化にある規範や道徳は、そもそも、そこで、他者と生きるために長年の人々の経験から生み出された叡智が大半であったと思われるからです。そうした知恵は、文化や宗教が異なっていても共通点がたくさんあります。嘘をついてはいけない、他者を傷つけてはいけない、殺し合ってはいけない、困っている人がいたら助けてあげなければならない、というようなことは、どの文化のどんな人にとっても、善悪を判断する上での、人間としての行動を決める原点のようなものだからです。
反面、宗教や文化は、とかく、人々に「線」を引かせたがります。自分の文化や自分の宗教だけが「優れた」「素晴らしい」ものである、と。時として、ある宗教の「神」は、異邦人を排除異教徒を改宗させることすら求めます。そして、とりわけ、それぞれの宗教集団や文化集団の中で権力を握っている人たちは、宗教や文化が持つこうした性格を悪用して、人と人との間に線を引き、人を戦地に送ったり、低賃金労働に就かせたりするものです。
シチズンシップは、権力者の言いなりにならない自由意志を持つこと
今、世界中で、貧富の差が拡大しています。
一つには、経済活動のグローバル化によって多国籍企業が世界中に市場を広げ、投資や労働に対して桁外れに莫大な利潤を得られる時代になったこと。もう一つは、技術革新によって機械やロボットが人間の労働にとって代わり、技術革新の恩恵を受ける、多くは高学歴の人と、それによって仕事を失う人とが真っ二つに分かれる時代になってきたことが背景にあると言えるでしょう。ほんのひと握りの資本家が持っている資本が、世界人口の貧しい方の半分の人々が持っている資本よりも大きいというほど、格差が広がった時代に私たちは生きています。
ところが、ほんとうに困ったことに、経済競争、労働機会競争で負けてしまう、いわゆる低学歴の人たちが、上のような社会の不条理に対して「連帯」し「団結」するどころか、持たざる者、負けている者同士が、文化や宗教の違いを理由に分断を深めていることです。アメリカやイギリスでのこの数年間の政治状況はそのことを露骨に見せてくれていますし、オランダはじめ、現在のヨーロッパの多くの国でも、貧困者の数は増え、こうしてますます小さくなっていく労働者の収益を、国粋主義に走る人々と、外国からやってきた移民とが、対立し、いがみあう、つまり、貧困に苦しんでいる人同士が対立し、お互いを排除し合う状況が出てきているのです。それを煽ることによって地位を得ようとする政治家が、今、世界中にどんどん増えてきています。
インクルージョンは見える他者を受容することから
同じことは、学校をめぐる教員と保護者の対立にも現れています。
学校の先生と自分の親とは、子どもたちが毎日日常的に触れている唯一の大人集団です。その大人たちが、学校という場所に線を引き、学校の中のことは教員の責任、家庭や近隣でのことは保護者の責任と分けてしまっている。分けるだけではなく、子どもに関して何かうまくいかないことが起きると、相手のせいにしようとしている。一人の子どもの発達を、教員と保護者とが両方から情報を共有しながら見守っていけば、様々なことがうまくいくはずなのに、お互いが、お互いの足りなさを隠し、協力して補い合うことを恐れている。こんなふうに、子どもの発達に直接関わっている大人たちがお互いに睨み合い分断している方が楽なのはいったい誰なのでしょう?
冒頭、普段は目に見えない地球の裏の他者の表情を読み取れる子どもたちの共感力の話は、多分、それだけ聞けば、誰でも「そうだ、そうだ」と納得する話なのかもしれません。それは、とりあえず、その遠くの人が、自分の生活圏にはおらず、直接自分に刃を向けてくる人ではないからでしょう。
むしろ、競走意識を感じるのは、自分のすぐそばにいる人、自分と同じキャリアを積もうとしている人、同じ学校で仕事をしている教員同士、同じ学校で同じ子どもに関わっている保護者と教員なのかもしれません。
だから、遠い国の話、世界はみんな仲間という美辞麗句を口に出す前に、まず周りを見回して欲しいのです。私たちは、自分の周囲にいる人、毎日見えている人たちを、真に「仲間として受け入れているのかどうか」ということを。
インクルージョンという言葉は、耳には気持ちよく響きます。でも、私たちは、本当に同僚や目に見える近くの大人たちに対して、受容的に行動しているのでしょうか? お互いを受容するということは、お互いが率直に自分の気持ちを言い合える関係にあるということです。
見える他者のことは棚に上げて、見えない他者との「平和」「国際協調」の話をしているのだったら、子どもたちはきっと「学校の先生がいつもお経のようにいっている単なるタテマエだよ」と、聞いているふりをしているだけで、真に深く考えることはないでしょう。インクルージョンは、子どもに教え諭すものではなく、大人が、今、ここで実践するもの、自分が受けてきた学校文化をもう一度見直し、そこから脱皮して学び直さなければならないものです。(続く)